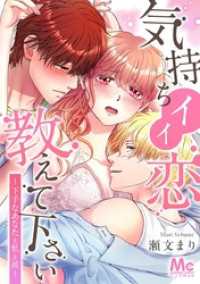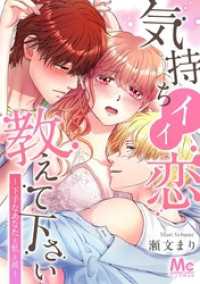内容説明
ベルクソン、フロイト、ベイトソンの思想、モリエール、カフカ、サルトルの文学、チャップリンやタチの映画などの新しい読解から、この永遠の謎の解明に一石を投じる、ブルデューとともにLiber叢書を立ち上げた現代フランスの知性による画期的な哲学エッセイ。
目次
夢と笑いの隠れた照応
ベルクソンの方法
びっくり箱、操り人形、雪だるま
狂気との関係
モリエール、越境する喜劇
滑稽さと不気味さ
滑稽さと不条理
“枠”という補助線
ベイトソンの視角
カフカ的宇宙、そして
フロイト“不気味なもの”
二重化と一体化
笑いという生の領域
著者等紹介
ジリボン,ジャン=リュック[ジリボン,ジャンリュック][Giribone,Jean‐Luc]
1951年、マルセイユ生まれ。エコール・ノルマル・シュペリウール卒。アグレジェ(高等教育教授資格者)となり、イェール大学でフランス語を教える。スーユ書店に入社し、La couleur des id´ees叢書を企画、さらに、ピエール・ブルデューとともにLiber叢書を立ち上げた
原章二[ハラショウジ]
1946年、静岡県伊東市生まれ。パリ大学博士(哲学)。現在、早稲田大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
K
13
ベルクソン『笑い』とフロイト『不気味なもの』の読解を通じてマラルメの述べていた「照応」に関する考察を行っている。コンパクトかつそこまで難しくない。滑稽さと不気味さは実は近しい関係という観点は非常に興味深い。ベイトソンの「枠」概念も取り入れている。「人はそれ自体笑うべきものである性格を笑うのではなく、ある特別な枠のなかに入った性格が滑稽だから笑うのである」と述べられている。そして、枠をもとにおかしさを付与できた時は、滑稽さを感じるが、枠に穴が開くと不気味に感じられるという。2021/08/24
里馬
5
(´c_`*)2010/11/23
スノーシェルター
4
ごめんなさい。間違えました。なんとなくしかわからない。フロイトとベルクソンを理解してから、読むべきでした。出直します。2010/09/21
鹿乃
2
ベルクソンの「笑い」は読み途中、フロイトの「不気味なもの」に至ってはまだ読んですらいない訳なのだが、滑稽で笑える事と不気味なものがどちらにも転び得るという考えは本書を読んで納得出来た。簡潔さが良いと思う。学術論文はかくあるべき(ダラダラ書かれると読むの疲れるし)。2012/10/04
林克也
1
笑いと不気味なものとの関係性に着目したところは敬服。 「人間は必然的に狂っているので、狂っていないということも狂気の別の様態において狂っているということである」パスカルーパンセ。納得。 2010/10/17