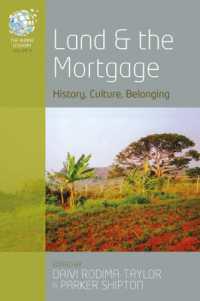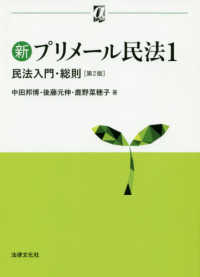内容説明
現代技術の本質は集‐立にある!人間を閉じ込めるこの命運からの脱却は可能か?思索の敬虔さとしての問い。
目次
技術への問い(一九五三年)
科学と省察(一九五三年)
形而上学の超克(一九三六‐四六年)
伝承された言語と技術的な言語(一九六二年)
芸術の由来と思索の使命(一九六七年)
著者等紹介
ハイデッガー,マルティン[ハイデッガー,マルティン][Heidegger,Martin]
1889‐1976。ドイツの哲学者。フライブルク大学神学部に入学、哲学部に転じ、1913年「心理主義における判断論」で博士号取得。15年同大学私講師となり、フッサールに師事、現象学を学ぶ。23年マールブルク大学教授、27年に主著『存在と時間』を公刊。28年フライブルク大学に移り、33年ヒトラー政権下、同大学総長に就任するが、在任期間1年たらずで辞任。30年代半頃よりニーチェ、ヘルダーリンへの関心を深め、36年から38年にかけて『哲学への寄与論稿』を執筆、後期思想の構想を明らかにする
関口浩[セキグチヒロシ]
1958年生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得。現在、早稲田大学社会科学部非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mstr_kk
7
現代技術の本質とは何か、それはいかにして生まれたか、それは人間と自然に何をもたらすのか、技術時代の危機から人間と自然を救うものの可能性はどのようなものか。そういった問題について、通俗的な観念を退けるため、語源学の方法を用いて論じた論考が収められた書物です。グローバル化した現代技術のシステムは西欧の形而上学の歴史によって規定されているので、それについて本質的に考え、間違った方向に進んでいるものを正すためには、原初というべきギリシアの語にまで戻って概念を検討することが有効だと、ハイデガーは考えたわけです。→2014/11/16
有沢翔治@文芸同人誌配布中
4
処女論文「ナトルプ報告」から晩年の「存在と時間」まで、〈ある〉という謎に挑み続けたハイデガー。彼は科学技術に対してどういう態度を取っていたのだろうか。また哲学との関係は? 荘子の無用の用を例にとって哲学を説明していく。https://shoji-arisawa.blog.jp/archives/51427793.html2014/05/05
ゆうちゃん
1
技術と科学や言語との関わりかたなどハイデッガー独自の解釈による技術論が古代ギリシャから現代に至る知見をもとに展開される。技術が駆動する自動走行の資本主義への警鐘を鳴らしていたハイデッガー。我々は人間側の自然回復期へと回帰せねばならない。2025/09/08
りっちー
1
技術を宗教や哲学になぞらえた読み物。思っていたのとは違っていたので、がんばって読みましたが、個人的には合わない書籍でした。2024/11/29
Violaの錬金術師
1
技術の本質を「問う」ことで思索の在り方をも問い直す。技術はあくまで人の道具である、のではない。むしろ自然やひいては人間の性質をエネルギーとしてや別の存在様式で開蔵する"Gestell"(集立)なのである。そこに人間の主体はあるのか?あるならばそれは問い立てる人間としてなのだろうか2013/02/05
-

- 電子書籍
- 新法令用語の常識(第2版)