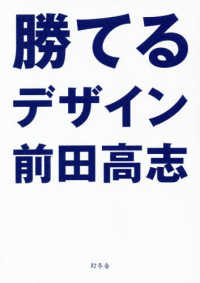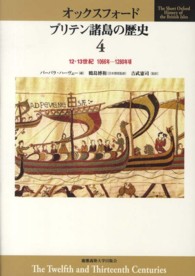出版社内容情報
宮本の撮った写真を、記録としての意義とともに優れた写真表現として捉えなおし、旅をそして日本を“写真に撮る”ことの意味を探る。
内容説明
『忘れられた日本人』で知られる民俗学者が撮った10万枚におよぶ写真を読み解き、その故郷を写す。
目次
旅人のまなざし―石川直樹が選ぶ48の写真(故郷;子ども;仕事;都市;移動)
周防大島を往く
著者等紹介
石川直樹[イシカワナオキ]
写真家。1977年生まれ。『NEW DIMENSION』(赤々舎)、『POLAR』(リトルモア)で日本写真協会新人賞。『CORONA』(青土社)で土門拳賞を受賞。主な著書『最後の冒険家』(集英社・開高健ノンフィクション賞受賞)
須藤功[ストウイサオ]
民俗学写真家。1938年生まれ
赤城耕一[アカギコウイチ]
写真家。1961年生まれ
畑中章宏[ハタナカアキヒロ]
作家・編集者。1962年生まれ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
新地学@児童書病発動中
118
民俗学者の宮本常一が取り続けた昭和の写真について考察する本。考察自体も悪くないのだが、圧巻はやはり宮本の写真。昭和が息づいている。もう一度昭和に帰って、昭和の空気に浸りきった気分になれる。ここに収められている写真の多くは、私より一世代か二世代前のものだが、ひたすら懐かしさを感じた。まるで祖母の昔話を聞くような感じだった。2015/10/11
ねこさん
24
写真点数はそれほど多くないので、宮本の仕事から民俗学的な日本の風景を眺めるのであれば別冊太陽の方が読み応えがある。宮本の写真を解説した本というより、写真に携わる人達が、宮本の写真がいかに記録以上のものであるかについて寄稿している本。写真を志す人には有益かもしれない。2022/11/29
きいち
24
宮本はもちろんプロの写真家じゃない。メモとして十万人分の写真を撮ってきた人。だから、小舟の藁の上に寝てる男の子の写真(別冊太陽の表紙にもなってる)だって、宮本自身の「影」が映りこんでしまっている。実際、プロじゃなく趣味で写真撮ってる人だって、そんなことしないだろう。十万枚の中にいい写真があったとしても、偶然としか思えないかもしれない。◇でも、違う、と写真家・石川は読む。「浮力がある」と。そうなのだ、前述の写真だって、写真として整っていたら、こんなに印象的ではないだろう。◇編者のひとり・畑中のコラムもいい。2014/11/14
三平
13
記録写真というより、興味あるものに対しふと向けた宮本常一の眼そのもののような写真たち。何かいろいろ写り込んでるし(笑) 切り取ったという感じより、写真を見ていると自分がそこに立って見ているような感じがしてくる。 特に元小学校教師だった宮本の子供たちへの優しい目線が伝わってくる写真がいい。見知った天満警察署前の鳥居の昔の風景が見れたのも嬉しかった。高麗橋近くに住み、桜ノ宮に通っていた宮本常一。昨日歩いた道は彼が歩いた道かもしれない。変わりゆく地元の風景をもう一度見直して焼き付けておこう。そう思った。2019/02/28
T M
10
石川直樹さんの写真展会場で発見。 宮本常一の著書は大好きなのだが、そう言えば写真をじっくり見たことなかったなと思い手に取る。そこには宮本の文章の世界と同じものが広がっていた。写真には“私”を入れないというのがルールだったようだけど、見る人によって判断は変わりそう。確かに一発でアートになるような狙った写真ではないのだが、ストーリーが見える写真なのだ。そこには宮本が滲み出ているとも言える。アラーキーが「写真をみているんでなくて、じかに(写っている)この人に会ってるという気になるんだよね」と。私も同じ気持ちだ。2017/08/20