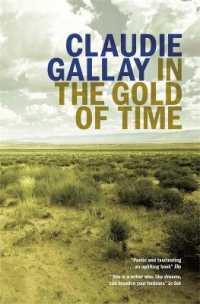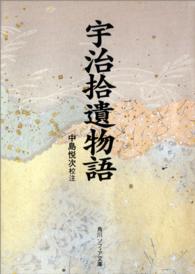目次
第1章 工学における設計の特質
第2章 心眼
第3章 近代工学の起源
第4章 図像化の道具
第5章 技術の知識の発展と普及
第6章 技術者の養成
第7章 見込みと現実のギャップ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アナクマ
30
【選書版で読了】「宇宙飛行士を月に送ったのは科学ではない。熟練した技術だ」にしびれる。◉主に2・6・7章。技術者にとって、科学や数学よりも重要なものは、さまざまな感覚的情報を集積し相互に関連づける経験を通じて養う心眼(=健全な判断と適合性や妥当性に対する直感)である。しかし重視されているだろうか、と。◉ 心眼という、言語に拠ることが難しい奥義について本書が十分に説明できているかどうかはひとまず措く(自動運転車の黎明期チャレンジに対する批判的目線なども)。だが、傾聴したい問題提起だ。再読必至。2019/02/11
Kazyury
2
山口周とのアナロジーでは、「エンジニアリングにおけるサイエンスに対するクラフトの優越」の主張。 本書では、クラフトの根幹として「心眼」を主題に据え、歴史的に心眼を如何に表現・養成してきたか、サイエンス偏重が心眼の育成を蝕んできたか、に多くの頁を割いている。 「心眼の表現」による意図伝達の重要性に比べ、心眼を正しく表現するケイパビリティが業界/技術者のレベルで不足している事に、一人のIT技術屋として危機感を覚える。広大な問題空間は理由の一つだとして、00年代以降のモデル化技法の停滞の根本には何があるのか。2019/04/03
ねこの
2
「設計」という行為の本質を突き詰め、技術者と技術者教育について論じる本。 機構と動作を「イメージとして」詳細に描くことこそが設計の本質であって、またその精度は経験によってのみ担保されるとする。 特に理論は不可欠であるとしながらも、設計という行為のうえでは経験を補佐するものにすぎないことを明確に注意している。2016/08/16
ireadertj
2
直感、実際に見たり、触れたり、感じたりすることによる設計の重要性を実感できた。これから、エンジニアに携わる人には読んでほしい。そして、この本のエンジニアは工学系を対象としているが、自分が仕事上関わるITシステムにおいても通じると感じた。ITのプログラムやシステムは物理的に感じることができないが、美しいなどと感じることが実際にできる。工学系以外においてもエンジニアは非言語的な思考を大切にしてほしい。2016/08/11
k
1
素晴らしい本。2022/03/12