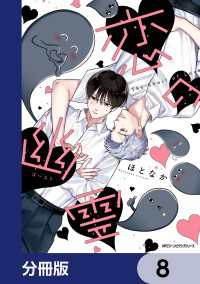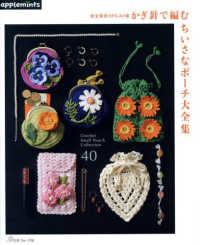出版社内容情報
偉大な父信玄の跡目を継いだ勝頼。彼の足跡や御家事情などを通して、大名の「戦争」の意味を探り、戦国大名像の真実に迫る。
内容説明
生き残りをかけて、信頼が問われた乱世―。個の実力のみに帰しては見誤る、武田氏滅亡への道。勝頼の「不運」とはいかなるものであったのか。その正体を探っていけば、戦国大名の本質が見えてくる。
目次
はじめに―勝頼は信長となにが違ったのか
第1章 勝頼の出生と高遠諏方氏相続
第2章 思いがけない武田復姓
第3章 武田氏の家督相続と不安定な基盤
第4章 長篠合戦
第5章 内政と外交の再編
第6章 甲相同盟崩壊と領国の再拡大
第7章 武田氏の滅亡―戦国大名の本質
著者等紹介
丸島和洋[マルシマカズヒロ]
1977年大阪府生まれ。2005年、慶應義塾大学大学院文学研究科後期博士課程単位取得退学。博士(史学)。専門は戦国大名論。国文学研究資料館研究部特定研究員などを経て、慶應義塾大学文学部非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
樋口佳之
26
戦国大名は「地域国家」と評価される運命共同体を作り出そうとしていた。これは、政治的フィクションの共有による産物/滅亡過程は実にあっけない。「軍事的安全保障体制」への信頼性を喪失した戦国大名が、挽回を図ることは実に難しい。/おわりにを先に読んだ方が著者の意図を理解しやすい内容でした。サブタイトル 試される戦国大名の「器量」がメインタイトルでもよかったかも2018/12/11
黒猫
23
武田勝頼が武勇に秀でただけの将で、大名としての資質に欠けたという定説。この定説に対して、著者は武田勝頼の生い立ちから、滅亡に至る過程をある程度武田家を知っている人を対象に書いている。専門書だと入りづらいけど、入門書だと物足りないと考えている人には是非オススメしたい本です。諸説あるけど、やはり北条氏を敵に回してしまったのが致命的だったと思う。家康の介入を阻止すべく外交を展開すべきだったのだろう。信玄は力で家康をねじ伏せたが勝頼にはできなかった。それが、勝頼と信玄の大きな差となって今の評価に繋がっている。2017/12/03
YONDA
21
平山優氏の「武田氏滅亡」とはまた違った視点で書かれている。平山氏は武田勝頼ではなく「諏方勝頼」であったことが、丸山氏は高天神落城が引き金となったと武田氏の滅亡を語る。こうやっていろんな意見が出てくるのが歴史の醍醐味。また、本書のなかで信玄が家康を独立大名ではなく、信長の従属国衆と認識していたこと。勝頼は信勝の陣代ではなく、正式に家督を継いでいたことなどの論は非常に興味深い。2018/03/25
月をみるもの
16
著者の名前をどこかで聞いたことがあるような気がしたんだけど、そうか「真田丸」の時代考証してた人なのか。。 昌幸パパが武田家で過ごした青春の物語としても読めるんだろうけど、自分にとっての本書は完全に「レイリ」の背景解説であった。。https://bookmeter.com/reviews/808133662022/05/07
MUNEKAZ
14
武田勝頼を通して描かれる「戦国大名」。その権力が武力に依る以上、配下の国衆に対する安全保障の担保が、戦国大名に求められる「器量」であるとする。長篠の敗戦以後、外交関係を再編し、新たな領地の獲得に成功しながらも高天神城落城の衝撃を乗り越えられなかった勝頼の姿はまさにというところ。そして、それは織田信長や北条氏政ら勝頼のライバルたちも同じ。信長が先進的で勝頼が後進的ということはなく、本質的には同質の軍隊を率いており、状況がほんの少し違えば、その運命は逆転していたかもしれない。2017/10/05