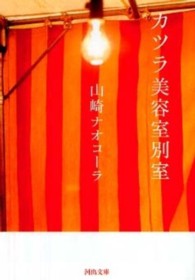出版社内容情報
「新しい文学ジャンルを創造した」と称される代表作の第2巻。
ミシェル・レリス[ミシェル・レリス]
著・文・その他
岡谷 公二[オカヤ コウジ]
翻訳
内容説明
死を飼い馴らし、正しく振る舞い、おのれの枠を超え出る…“生きる/書く”信条の一件書類。
著者等紹介
レリス,ミシェル[レリス,ミシェル] [Leiris,Michel]
1901年パリ生。作家・民族学者。レーモン・ルーセルの影響を受け、20歳ころより本格的に詩作を開始。やがてアンドレ・マッソンの知遇を得て、1924年シュルレアリスム運動に参加。1929年アンドレ・ブルトンと対立しグループを脱退、友人のジョルジュ・バタイユ主幹の雑誌『ドキュマン』に協力。マルセル・グリオールの誘いに応じ、1931年ダカール=ジブチ、アフリカ横断調査団に参加、帰国後は民族誌学博物館(のちの人類博物館)に勤務、民族学者としての道を歩む。1937年バタイユ、ロジェ・カイヨワと社会学研究会を創立。戦後、ジャン=ポール・サルトルらと雑誌『タン・モデルヌ』を創刊。1990年没
岡谷公二[オカヤコウジ]
1929年東京生。東京大学文学部美学美術史学科卒業。跡見学園女子大学名誉教授。著書に『南海漂蕩』(冨山房インターナショナル、和辻哲郎文化賞)など。訳書も多数ある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
syaori
44
死と友情、恋を巡って展開する本巻で語られていたのは個と世界の関係だったように思います。「他人との距離」が取り払われ、魂の触れ合いともいうものを感じた体験を語る戦役での回想が印象的で、現在の作者はそれを幻想だったようにも思うのですが、虚か実か、二つの思いに引き裂かれ、過去と現在の狭間から立ち上る物語はある種の神話性を帯び「真実よりも一層真実なもの」として迫ってきました。人間同士の和合を一瞬でも信じられること、そしてそれを描くこと。これが「人生というゲームを処するため」に探していた規則なのでしょうか?次巻へ。2018/07/20
踊る猫
24
死。それが色濃く影を落とす。ミシェル・レリスの人生は不勉強にして知らないのだけれど、彼自身が自分の実存/人生において危機を感じた時期に書かれたのだろうか。言葉遊びは相変わらず洒脱で、やはりレリスは母国語で吃る優れた書き手なのだなと思わされた。第一巻では言葉遊びに終始/自家中毒していた気がしたが、ここに来てグッとストーリーが動き始めたようにも思われる。これは先が楽しみ。アクチュアルに動き続ける作家としてのレリスの面目躍如といった感があり、積読の『幻のアフリカ』共々残された著作を読み進めたいと思った次第である2019/07/14
-

- 電子書籍
- ドル化とは何か ──日本で米ドルが使わ…