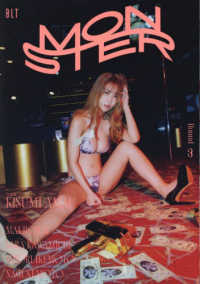出版社内容情報
ヴァナキュラーな側面を含め、写真のもつ様々な機能を、主にテクストとの関係性において分析した13の珠篇。バルト、ベンヤミン、ソンタグら定番を超えたイメージ論の新地平。
内容説明
写真論の新地平をひらく十余篇。
目次
1 文学の辺境―写真小説小史(幽霊を知らぬ頃―シャンフルーリ、バルザック;時のゆがみ―ローデンバック、ブルトン、ゼーバルトの写真小説;プルーストと写真―記憶、知覚、人間関係の比喩として;エルヴェ・ギベールと写真;写真への抵抗―フランス現代小説と写真;写真の現場から 写文字の話)
2 シュルレアリスムによる写真の変容(退屈だからこそ感動的な写真と出会うために―ブルトン、バルト、「ヴァナキュラー写真」;革命家たちの凡庸なスナップ写真―シュルレアリスム、写真、オートマティスム;ピエール・モリニエ―シャーマンと自己中心主義;クロード・カーアンのセルフポートレート―小さい写真;写真の現場から ダイヤモンド・ヘッドと水田)
3 写真論からイメージ論へ(透明で不透明な像―ロダン“バルザック記念像”をめぐって;すでになくなっているそれを見送ること―ピエール・マッコルランと写真;アンリ・カルティエ=ブレッソン、アメリカ、一九四七年;サルトルのイマージュ論―不在の写真をめぐって;『喪の日記』から『明るい部屋』へ―《温室の写真》をめぐるフィクション)
跋 写真の何が変わったのか
著者等紹介
塚本昌則[ツカモトマサノリ]
1959年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退/パリ第12大学文学部博士課程修了。現在、東京大学大学院人文社会系研究科教授。ヴァレリー研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
内島菫
きつね
子音はC 母音はA
コバ
-

- 電子書籍
- 悪役に正体がバレてしまった【タテヨミ】…