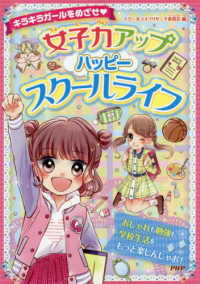出版社内容情報
文化学園服飾博物館が所蔵する三井家の逸品
文化学園服飾博物館の所蔵資料を、日本、ヨーロッパ、アジアなどに分類。実に時代や地域などによってまとめ、世界の服飾・染織文化を概観できるよう叢書として刊行。本書はその初刊。
文化学園服飾博物館所蔵三井家のきものについて
三井家略系図・円山派画系図
三井家、応挙略年表
本書をお読みいただく方に
江戸後期の小袖
三井家のきものに見る応挙様式 樋口一貴
応挙模様の誕生 道明三保子
明治・大正のきもの
写真抄―三井家当主夫人の着こなし―
男子と子供のきもの、掛袱紗
用語解説
文化学園服飾博物館所蔵、三井家のきものの分類と内容 植木淑子
応挙と松竹梅図 河野元昭
参考文献
「世界の服飾・染織」刊行に寄せて 大沼 淳
目次
1 江戸後期の小袖(三井家のきものに見る応挙様式;応挙模様の誕生)
2 明治・大正のきもの(写真抄―三井家当主夫人の着こなし)
3 男子と子供のきもの、掛袱紗
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ショア
23
豪商三井家の江戸時代から近代までの着物解説。明治以降よりも江戸時代の着物の方が遥かに派手で雅で優雅。歌舞伎者的な色調とダイナミックな下絵と派手な刺繍。明治以降は色味や裾付近にワンポイントなどシック。飾り兜の世界にも近い感覚。2025/02/23
定年(還暦)の雨巫女。
5
《私-図書館》【再読】貴族や武家とは違い、色はシックだが、構図とかは、大胆。2018/02/10
石油監査人
4
この本は、旧財閥の三井家が所有していた、江戸時代からの着物や帯などを、現在の管理者である文化学園服飾博物館が、詳しく解説したものです。年代的には、江戸後期から大正期にかけてのものですが、特に、江戸時代の着物は、色彩の豊かさと、日本画の下絵を基に表現した大胆なデザインが特徴的で、芸術性の高さは、他の時代とは一線を画しています。三井家と日本画家の円山応挙との密接な交流についても解説されており、両者が現代のアパレルブランドと専属デザイナーのような関係でもあったことを知り、とても興味深く感じました。2019/08/02
雨巫女
3
さすが、三井家の着物。色や素材はもちろん。見えない部分や着物の構図等、残っていてよかった。2010/05/27