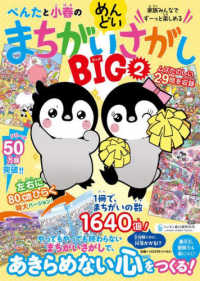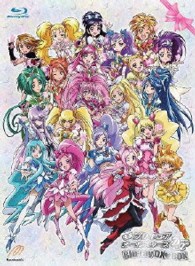出版社内容情報
古地図・地形研究の最尖鋭・芳賀ひらくによる、江戸と東京の古地図地形図を徹底比較した超マニアックな東京散歩ガイド。
内容説明
江戸の古地図には、当時の地形までもが刻み込まれていた。古地図と現在の地形図を比較することで、約400年のわれわれの暮らしが浮かび上がる。多くのメディアにて古地図の魅力を語ってきた著者が案内する本物の古地図の世界。
目次
水道橋(寛永19年(1642)頃/明治16年(1883)頃)
丸の内・日比谷(慶長7年(1602)頃/明暦3年(1657)頃/明治42年(1909)頃/平成14年(2002)頃)
神保町(寛永19年(1642)頃/平成14年(2002)頃/嘉永3年(1850)頃/延宝年間の図/明治20年(1887))
銀座(寛永19年(1642)頃/安政6年(1859)頃/大正10年(1921)頃/平成14年(2002)頃)
人形町・元吉原(寛永19年(1642)頃/明暦3年(1657)頃/安政6年(1859)頃/平成14年(2002)頃)
西片・白山・小石川(寛永19年(1642)頃/明暦3年(1657)頃/安政6年(1859)頃/平成14年(2002)頃)
赤坂(寛永19年(1642)頃/明暦3年(1657)頃/安政6年(1859)頃/平成14年(2002)頃)
麻布(寛永19年(1642)頃/明暦3年(1657)頃/明治16年(1883)頃/平成14年(2006)頃)
六本木・元麻布(寛永19年(1642)頃/明暦3年(1657)頃/安政6年(1859)頃/平成14年(2002)頃)
芝・三田(寛永19年(1642)頃/明暦3年(1657)頃/安政6年(1859)頃/平成14年(2002)頃)〔ほか〕
著者等紹介
芳賀ひらく[ハガヒラク]
1949年仙台市生まれ。元柏書房代表取締役社長。現、之潮(コレジオ)代表。日本地図学会評議員。淑徳大学公開講座講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あなほりふくろう
りー
たくのみ
マギー
takao
-
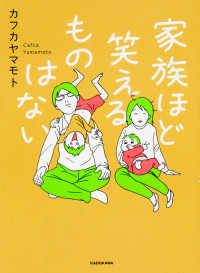
- 和書
- 家族ほど笑えるものはない