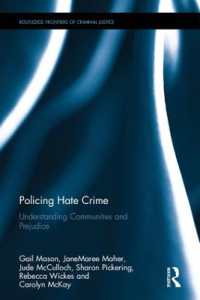内容説明
世界中のどこに行っても、技術はけっして裏切らない。理論派解説者・風間八宏が、いま改めて選手の「個人技」を問う。
目次
序章 技術はけっして裏切らない
第1章 「個人戦術」で掴む勝利への布石(個人戦術は「考える力」と「技術」の集合体;個人戦術を重視=チーム戦術の軽視ではない ほか)
第2章 戦える「技術」―止める・蹴る・運ぶ・外す(大切な基本技術が本当に身についているか;0.5秒の技術の差が分けるゲームの明暗 ほか)
第3章 日本サッカーに必要な「確かな指導力」(「部員5人」からスタートした私の監督人生;教え子が自ら切り拓いた輝かしい道 ほか)
終章 日本にも「当たり前のサッカー」を
著者等紹介
風間八宏[カザマヤヒロ]
1961年、静岡県生まれ。筑波大学蹴球部トップチーム監督・日本サッカー協会特任理事・Jリーグ理事・サッカー解説者。筑波大学卒業後、ジョイフル本田を経て、84年からドイツのプロリーグで5年にわたり活躍。帰国後はサンフレッチェ広島に入団、主将としてステージ優勝に導くなど、Jリーグの創成期を大きく盛り上げた。その後、再びドイツでプレーし、97年に現役引退。現在は母校・筑波大学の蹴球部監督として指揮を執る傍ら、「清水スペシャルトレーニング」(静岡市)や「トラウムトレーニング」(つくば市)などでも選手の育成に取り組む(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
anco
13
当時、筑波大学蹴球部監督(現、川崎フロンターレ監督)の風間八宏さんが指導法を中心にサッカーを語った一冊。サッカーをしていくうえで選手に求められるのは、考える力と技術からなる、個人戦術。自分は何ができるのかを常に考えることと、止める、蹴る、運ぶ、外すといった基本技術の重要性を強調。戦うためにはコミュニケーションをとるより先決なことがある場合も多々ある。斬新な戦術論ではなく、サッカーをシンプルにとらえているあたりはクライフのサッカー論にも通ずるところがあるように思えました。2015/03/13
ふろんた2.0
13
川崎フロンターレ監督就任前の本ですが、考え方は近著と変わらない。筑波大の学生を指導していた分、基本的な技術とメンタル面に重点が置かれていると思います。ところで、ヤッヒーの戦術はかなり独特なので、試合だけ観てるサポーターは著作を1つくらい読んでおかないと実際のところがわからないんじゃないかな。2014/06/22
とりもり
3
日本が誇るべき智将、風間八宏によるサッカーに対する心構えを説いた本。「個人戦術」(選手一人ひとりの戦う術)には、「考える力」と「技術」の2つが揃っていなくてはならない。更に、指導者が指示するのではなく選手自らが考えることの重要性、「技術」を身につけることはあくまでも目的を達成するための手段であることなどが、何度も強調される。これって、何もサッカーに限った話ではなく、全てのことに共通する基本だよなぁと納得。こんな指導者に出逢えた選手は幸せだろう。他の本も読んでみたいと思った。オススメ。★★★★★2015/02/20
ズカ
2
「考えること」と「技術」のバランスが大事だと言うことが伝わる本でした。監督が決めた戦術が重要でなく、大事なのは「こういう状況の時に、自分はどうするか」という考える力をみにつけること。サッカーをしたことない素人感覚ですが、子供がいれば読ませてみたいなぁと思いました。2013/10/12
ご〜ちゃん
2
「大人たちが状況判断の場を奪っていくことで、子どもが自分で考えられなくなってしまう場面は多々見受けられます。」という一文。自分で判断させる癖をつけるように導いてあげているか、もう一度考えるきっかけとなりました。2012/11/24
-
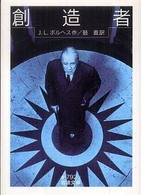
- 和書
- 創造者 岩波文庫