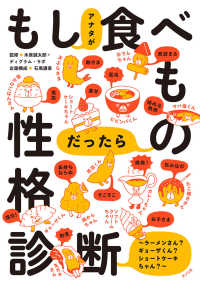内容説明
明治になって衰退する柔術界に、新星のごとく「講道館流」が誕生した。提唱者は文武二道の達人、嘉納治五郎である。技のたゆまざる追究と人間教育への情熱によって、「姿三四郎」のモデルとされる志田(西郷)四郎ら「四天王」がめきめきと頭角を現す。若き気概に充ちた、闘う漢たちの壮大な物語が、いま幕を開ける。
著者等紹介
夢枕獏[ユメマクラバク]
1951年神奈川県生まれ。77年、SF文芸誌『奇想天外』にて「カエルの死」でデビュー。89年『上弦の月を喰べる獅子』で第10回日本SF大賞、98年『神々の山嶺』で第11回柴田錬三郎賞を受賞。2011年から12年にかけて『大江戸釣客伝』で第39回泉鏡花文学賞、第5回舟橋聖一文学賞、第46回吉川英治文学賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
姉勤
40
明治維新後、古き無駄なものとして廃れようとした柔術を、柔道としてまとめ後世に残した男、嘉納治五郎の物語。虚弱の体を鍛えるため志した柔術だが、その面白さに魅了され数多の流派を学んでいく。以前は、講道館柔道以外の柔術を認めず排除していった偏見があったが、その逆で帝大講師の立場を使って、社会の公器として広めていった人物と改まった。そんなことより達人たちの格闘が大変面白い。2024/03/18
T2y@
25
夢枕獏の初読作。 嘉納治五郎と講道館の戦記、実に面白い。500ページ弱も一気に読み。 木村政彦とエリオグレーシー戦からの書き出しもニクい(笑)。 文士であり武道家、明治の進みゆく西洋化の中で、和魂を柔道として昇華させ、やがて世界に広めていく、これからの戦いぶりが早くも愉しみ。 志田(西郷)四郎のニヒルな描写もたまらない。2014/12/13
眠る山猫屋
18
まずは紹介編といったところか。実在の人物たちを描くという縛りが、いつもの獏さんの軽快さを奪っているものの、圧倒的な熱量は健在。嘉納治五郎という名前だけは知っていた人物像が、気持ちよく崩されていく。こんなに文武両道の男が存在したんだなぁ。そして治五郎門下の野獣のような男たち。一気読み必至。2015/10/16
ぶんぶん
16
【古本屋】す、凄い、嘉納治五郎の生き方に感動する。 消え去りゆく「柔術」それを淘汰して「柔道」を確立する治五郎、試合の在り方にも一工夫がある。 獏流・冶五郎伝、先ずは四天王の成り方たちから披露、凄まじい猛者ばかりだ。 しかし、嘉納治五郎が文武の才がある事の驚き、明治の時代がぐんと近くなって来た。 続いて2巻へ。2023/10/21
Syo
13
これまた面白い 作者も言ってるし2024/04/10