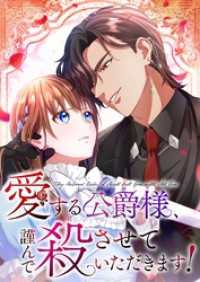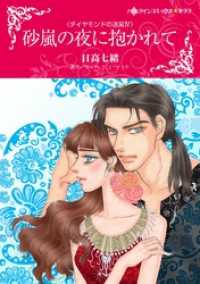内容説明
高校の修学旅行で人形浄瑠璃・文楽を観劇した健は、義太夫を語る大夫のエネルギーに圧倒されその虜になる。以来、義太夫を極めるため、傍からはバカに見えるほどの情熱を傾ける中、ある女性に恋をする。芸か恋か。悩む健は、人を愛することで義太夫の肝をつかんでいく―。若手大夫の成長を描く青春小説の傑作。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





乱読本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
636
三浦しをんさんお得意のお仕事小説なのだが、今回はそのお仕事がいたって特殊。文楽の若き大夫なのである。文楽の世界に飛び込んだ健の、文楽においての、そして人間としての成長物語として描かれる。各章のタイトルは、例えば『女殺油地獄』や『日高川入相花王』などと文楽の演目をあてている。しをんさんの意気込みも気合も十分。最終章『仮名手本忠臣蔵』6段目勘平切腹の場での「ヤア仏果とは穢らはし。死なぬ死なぬ。魂魄この土に止まつて、敵討ちの御供する」はもう圧巻。まさに浄瑠璃の「虚」の空間が「実」に飛翔する。それを描くしをん⇒2025/01/01
hiro
409
作者は二ヶ月に一度大阪へ文楽を見に行くとエッセイに書いているので、余程文楽が好きなのだと思っていたが、この本を読むと文楽に対する作者の思いが伝わってくる。主人公は就学旅行で文楽の虜になり大夫となったが、30歳を超えて芸と恋に悩む“青春?小説”。文楽の演目と主人公のリアルな恋と芸への悩みが重なりあい、それをクリアして主人公は成長していくところが、ここがこの小説の一番の見所。ただ文楽の知識があれば、より一層楽しめるだろう。また、大阪人としてもまったく、台詞の大阪弁は気にならなっかたところもしをんさん流石。2011/08/07
kishikan
403
本のカバーをよく見ず、また「仏果」という意味も分からずに購入してしまったため、この本が文楽に関した小説だとは知りませんでした。文楽は見たことはありませんが、歌舞伎は何度か見ていますので、浄瑠璃や演目も含め興味深く読みました。それにしても、三浦さんの文楽という芸の奥深さを描く筆力には、素晴らしいものがあります。加えて、愛の成就と芸を極める困難さ、その狭間で揺れる主人公「健」の心を文楽の演目に重ねているところなんて、さすが!それに何よりこの小説を面白くしているのが、ミラちゃんのコマッチャくれた可愛さでしょう。2011/09/28
佐々陽太朗(K.Tsubota)
368
一流のものだけが一流を知る。一つのものを至上と思い定めて他のものは失っても仕方なしと覚悟する。そうしなければ到達できないほどの高み。それほどの高みがあることを知るのは、その高みに至る途上にあってなお上をめざす者だけなのだ。子供は自分の限界を知らない。いずれは死ぬ運命にあることを今は意識していない。しかし、大人は、それも道を究めようとする者ならばなおさら己の限界を知っている。残された時間があまりに短いことも。本当に富士山に登ろうと決めた者だけが富士の頂に立つことが出来る。散歩のついでに登った者はいない。2012/08/09
さてさて
351
『もし文楽の神さまがいるのなら。健は楽屋の通路を歩きながら願った。俺を長生きさせてくれ。もらった時間のすべてを、義太夫に捧げると誓うから』。そんな思いの先に『大夫』の道を極めていこうとする主人公の健。この作品ではそんな健の姿を通して『文楽』の舞台裏を興味深く覗き見ることのできる物語が描かれていました。『文楽』の奥深さを感じるこの作品。そんな『文楽』にかける人の思いの深さに感じ入るこの作品。『文楽』に興味のある方はもちろん、どんなものか覗いてみたいという方にも是非手にしていただきたい、熱い、熱い物語でした。2025/01/11