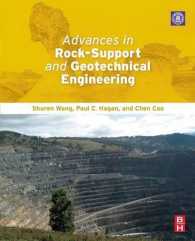出版社内容情報
最新技術で、漁業・養殖業が成長産業に!
日本の水産業は、水産資源の減少、就業者の減少・高齢化などの課題をかかえていますが、持続可能性を考えた資源管理やICT・AI・ロボットなどの技術で、成長産業へと変わろうとしています。日本にとっての水産業の重要性や、漁業・養殖業を効率化・省力化するスマート水産業の技術を、事例とともに紹介します。
第1章 水産業の現状と課題
日本の漁業の歴史と生産量の推移/とりすぎや環境の変化で魚が減少/漁業就業者の減少、高齢化/世界では魚の消費量が増加/世界の水産資源は大きく減少/日本にとっての水産業の重要性/水産資源管理の取り組み/スマート水産業で課題解決へ
第2章 スマート水産業・さまざまな技術
漁獲情報のデジタル化で資源管理/計量魚群探知機で漁獲量をコントロール/人工衛星を利用して漁場を予測/バイオロギングで漁場を探索/定置網内の魚群をいつでも探知/熟練漁師のノウハウをAIで再現/カツオの一本釣りロボット/人工衛星やスマートブイで赤潮を監視/AIえさやり機で毎日の作業から解放/魚体測定をAIで自動化/スマート陸上養殖/魚種の選別と加工をAIとロボットで自動化/市場・流通のデジタル化/操業中に漁獲情報を市場と共有
もっと知りたい!
漁業のおもな種類/養殖業の課題/資源評価の取り組み/地球にやさしい、持続可能な消費を心がけよう/地球観測衛星とは?/バイオロギングで海の生物の生態が明らかに/「入札」って何?
こちらも注目!
日本人の魚ばなれ/激減したクロマグロが回復するきざし/人工衛星で違法操業がわかる/水中ドローンの活躍/海面の画像で、むだなえさを削減/超音波を使い、魚の数をカウント/ホタテ貝から自動でウロを取りのぞく/産地と食品スーパーを結ぶマッチングアプリ/石垣島のマグロ漁でも、「あげ縄」後すぐに情報共有
目次
第1章 水産業の現状と課題(日本の漁業の歴史と生産量の推移;とりすぎや環境の変化で魚が減少;漁業就業者の減少、高齢化;世界では魚の消費量が増加;世界の水産資源は大きく減少;日本にとっての水産業の重要性;水産資源管理の取り組み;スマート水産業で課題解決へ)
第2章 スマート水産業・さまざまな技術(水産資源管理1 漁業情報のデジタル化で資源管理;水産資源管理2 計量魚群探知機で漁獲量をコントロール;漁場探索1 人工衛星を利用して漁場を予測;漁場探索2 バイオロギングで漁場を探索;定置網漁の効率化 定置網内の魚群をいつでも探知 ほか)
著者等紹介
和田雅昭[ワダマサアキ]
公立はこだて未来大学システム情報科学部情報アーキテクチャ学科教授。同大学マリンIT・ラボ所長。1971年、静岡県焼津市生まれ。宮城県仙台市育ち。北海道大学水産学部卒業。同大学院水産科学研究科修了。博士(水産科学)。株式会社東和電機製作所を経て、2005年、公立はこだて未来大学に着任。2012年より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あみやけ
こぺたろう
SHUE
ビッグマックツトム