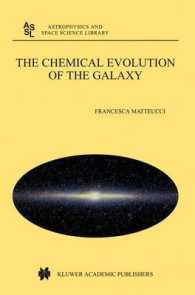出版社内容情報
先史より、人類が病に倒れ、抗ってきた「感染症」と「文化」には共通性がある。両者の不可分性から人間社会の本質を明らかにする。
内容説明
集団の人口が多いほど技術水準は高い?イノベーションは「誰かの失敗」から生まれる?「文化進化」の視点からヒトが「つながる」功罪を考える。
目次
はじめに―人類史の研究の「不確かさ」
第1章 感染症と文化の伝達の共通性
第2章 社会の「複雑化」と感染症
第3章 集団脳・イノベーション・社会ネットワーク
第4章 人類は病をどう防ごうとしてきたか
おわりに―情報空間の「感染症」と人類史研究の将来
著者等紹介
田村光平[タムラコウヘイ]
東北大学学際科学フロンティア研究所・東北アジア研究センター准教授。2013年、東京大学博士課程修了。博士(理学)。東京大学特任研究員、ブリストル大学特任研究員、東北大学助教などを経て2022年より現職。専門は人類学、文化進化(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
タカナとダイアローグ
16
人類史の定説は次々と覆されていくことを前提としたとして、現在の論点を広く紹介してくれている因子。グランドセオリーで説明するハラリがいて、論点を一般向けに紹介してくれる著者のような研究者もいて、厳密な研究を続ける研究者もいる。集団脳という考え方らしい。感染症への対応するとしての集合・離散や、下戸の説、行動免疫など、新しく知ることが多かった。数年したら読み直したい。有益と害がトレードオフの関係になったとき、シミュレーションでわかることが多いんだろうなと思った。気になっていた人類精神史を読むことにした。2023/12/15
izw
8
人間があつまり、つながることで、技術は発展し、感染症も流行する。人類進化の痕跡は直接残っていないことが多いので、種々の間接的証拠を元に、仮説を立て、検証を続ける。そんな現在進行形の研究分野で、確実なものがない中で、何が語れるのか、語ってよいのか、と悩む著者の姿が垣間見える。新たな遺跡の発見、分析手法の進化により、日々進んでいる研究の一端を伺うことができると同時に、つながりにより、知識が共有され、集団脳として、文化として、進化していく、それに伴い感染症も進化し、流行する、という相関があることは確からしい。2023/06/05
げんさん
2
「下戸」の理由はアルコールが分解されてできるアセトアルデヒドが長時間分解されずに血中に留まっているからです。ということは、血管中の寄生体、たとえばマラリア原虫やアメーバも長時間アセトアルデヒドにさらすことになります。その結果、寄生体を排除しやすくなります。下戸であることが、寄生体が増殖することへの防御になるのです。この「下戸」になる遺伝子が生まれた年代を調べると、農耕の開始期に近いと主張されています。つまり、農耕により高まった感染の危険性への対抗策として進化したと推測しているのです。2023/08/11
takao
2
ふむ2023/05/16
ひろこ
1
読み終わりました。人類史の概観でした。集団脳(人が多いほど知が集まるし、人が多いほど知が高くなる。)と感染症(感染症も人が多いほど広がる。人との交流で感染症が広がる。例外もある。)の正の関連を謳った本でした。数式は読み飛ばしました。新しい本なので、コロナもペーボのノーベル賞も触れられています。2025/08/18