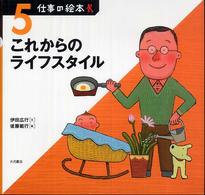出版社内容情報
昔はなかった日本独自の“てんまる”。
●なくてもすんでいたのになぜ?紆余曲折を経て採用することになった理由と歴史的背景を探る。
「ここではきものをぬいでください」。こう書かれた文章があったら、「履物」か「着物」か、どちらの意味か迷うだろう。短い文でも読点がないと、このように意味をとりづらい。句読点の目的は、コミュニケーションの大基本「正しく伝えるため」だったのである。
●日本では奈良時代から、一部でさまざまな句読点らしきものはあったが、いまの形になったのは明治時代。江戸時代後半、当時の学者たちによって、ヨーロッパのパンクチュエーション(記号)と「てんまる」が比較されたことが基盤を作ったといえる。この時こそ、日本語が近代化する革命的ターニングポイントだったのだ!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
keroppi
86
図書館の新刊コーナーで目に止まった。「てんまる」って何?「、」と「。」、つまり句読点。句読点の始まりから、その歴史、現代文学やマンガでの使われ方まで。今までそんなに意識していなかった句読点だが、こういう風に見てみると、実に興味深い。自分でも、いつどういう時に「てんまる」打っていたんだろうと考えてしまう。マンガのところで、小学館の少年コミック、青年コミック以外には「てんまる」を使うことがないと書かれていた。え、ほんと?と手元にあったマンガ本を数冊見てみたら確かにそうだった。ビックリ!2022/10/13
きみたけ
64
先日京都にある漢字ミュージアムに奥さんと行きました(本当は子どもたちも連れて行きたかったのですが拒否られました😅)。この本はミュージアムに併設の図書コーナーで紹介されていた本です。著者は日本の中国文献学者で大東文化大学教授の山口謠司先生。昔はなかった日本独自の「てんまる」(句読点)について、紆余曲折を経て採用することになった理由と歴史的背景を探った一冊。句読点について考察した本などなかなかないのでとても興味深かったです。2022/08/02
ネギっ子gen
53
「てんまる」は、明治の「言文一致運動」から生まれた。「ここではきものをぬいでください」。この例文。「履物」か「着物」か迷う。短い文でも読点がないと意味を取りづらい。句読点の目的は、コミュニケーションの基本「正しく伝えるため」のもの。過去から現代日本語までの「、」「。」の歴史について詳しく記し、日本語の可能性を探る本。【結婚式の招待状】<「てんまる」は、文章を「切る」ものなので、二人の「絆を切る」ことになるという縁起を担いで、結婚に関する挨拶状、招待状には「てんまる」を入れないことになっている>。そっか。⇒2022/10/08
ま
37
日本語におけるてんまる(句読点)の歴史はそこまで古くない。読み言葉から書き言葉へ、さらに書き言葉でも音読重視から黙読重視へと梶を切ったとき、てんまるが存在感を示し始める。日本語を少しでも意味明瞭な言語にしようという近代化の意図もあったようだ。2022/11/19
kei-zu
25
本書にも紹介がある公用文に関する仕事をしており、商業出版もさせていただいている立場から、非常に興味深い内容。 黙読と音読の読点の位置や頻度の違いは、スピーチ原稿を書くようになって感じていましたが、指摘されてなるほど。江戸時代のオランダ語の解説が句読点の分析の端緒とは知りませんでした。 そうそう、京都市の横書き条例は「,」「。」だったものを、国のこの度の通知により、先ごろ「、」「。」に改めたそうです。2022/10/29
-
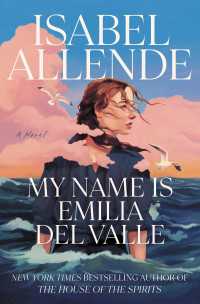
- 洋書電子書籍
- My Name Is Emilia d…