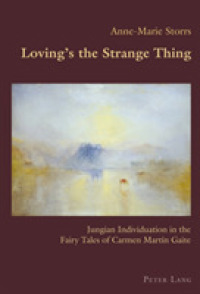出版社内容情報
小林製薬はなぜ、20期以上も連続増益・増配ができているのか。なぜ、長年愛されるヒット商品を創出し続けることができるのか。なぜ、人を惹きつけるネーミング、キャッチコピーを生み出すことができるのか――。
アンメルツ、ブルーレット、消臭元など、衛生日用品のニッチマーケットで勝ち続けてきた小林製薬。この成長企業を率いてきた根っからのマーケッターが、初めてその経営の秘訣を語り明かす。同族経営が成長・飛躍し、社会の役に立つ企業であり続けるための実例がここにある。
<目次より>
●創造は「よいものの模倣」から始まる
●ブランドを育てるとともに「らしさ」を追求する
●「少しつくって、少し売り、さらにもう少しつくる」という考え方
●会社にも人間にも成長過程がある
●「失敗は堂々と語る」文化を大切にする
●強いボールを投げ続ける
●現場を知れば、最悪の事態もイメージできる
●「実績を上げる」ことが先決だ
●「あと一日考える」ことの大事さ 他
内容説明
アンメルツ、熱さまシート、サワデー、ブルーレット、消臭元、サラサーティ…長年愛される商品を創出し続け、23期連続増益・22期連続増配の成長企業を率いてきた根っかりのマーケッターが、開発秘話とともに、事業躍進の秘訣を初めて語り明かす!
目次
すべては「“あったらいいな”をカタチにする」ために
第1部 アイデアをヒットさせる経営―私の体験的経営論 マーケティング戦略編(「わかりやすさ」への挑戦;「サムシング・ニュー、サムシング・ディファレント」の追求;新製品開発に生きる)
第2部 社員の幸せを第一にする会社へ―私の体験的経営論 組織・人材マネジメント編(アイデアを生みだす仕掛けづくり、その源流へ;よき社風の創造と継承;全社員経営の道を歩み続ける)
第3部 逆境と失敗を未来の糧とする―私の体験的経営論 経営哲学編(「為せば成る」の執念が道を拓く;失敗から学んだ経営の心―驕らず、謙虚に)
著者等紹介
小林一雅[コバヤシカズマサ]
1939年兵庫県に生まれる。小林製薬二代目社長・小林三郎の長男。大学在学中、父が早逝し、甲南大学経済学部を卒業後、62年3月に小林製薬に入社する。64年の米国視察旅行をきっかけに、65年、コロンビア大学に留学。66年11月に同社取締役、70年11月に常務取締役を経て、76年12月、四代目社長に就任。医薬品の卸業であった小林製薬を衛生日用品・医薬品のメーカーへ転換、事業を伸展させた。2004年に会長に就任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Naota_t
メチコ
モビエイト
-
たけ
-

- 和書
- 森林社会学への道