- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 日本の哲学・思想一般(事典・概論)
出版社内容情報
没後三十年。真の知識人「山本七平」の叡智が時を越えて光彩を放つ――。日本社会で営々と築き上げられてきた「働き方」を変革していくことが、近年の社会環境や生活様式の変化と相まって、急速に求められています。しかしながらその「働き方」の根底にある日本人の労働観、さらには「仕事の思想」といえるものを私たち日本人はどのように把握し、どれだけ意識してきたといえるでしょうか……。かつて、この日本人の労働観の原点というものに着眼し、その考究に情熱を傾けたのが故・山本七平氏でした。本書ではまず序章で山本氏が捉えていた日本人の「仕事の思想」の系譜の再把握を行い、以降の章で、日本思想史上、山本氏が重要視する人物(最初の日本教徒・不干斎ハビアン、そして鈴木正三)への理解を深め、さらに江戸期から近代の渋沢栄一まで、「仕事の思想」がどう繋がるかの論究を試みています。著者は石田梅岩の研究で知られる気鋭の思想史学者です。
内容説明
どう働き、どう生きるか。『日本資本主義の精神』『近代の創造―渋沢栄一の思想と行動』『勤勉の哲学』といった山本日本学の代表的名著を道標に、気鋭の思想史学者が挑む意欲作!
目次
序章 山本七平が捉えた日本人の「仕事の思想」―その慧眼に映し出された輪郭を辿る(山本日本学と「暗黙知」;キリスト教と戦中・戦後体験 ほか)
第1章 「仕事の思想」のはじまり―戦争を必要としない社会に起きた大転換(起点としての江戸期;現代日本にまで繋がる「日本教」 ほか)
第2章 商人が躍進した社会に現れた思想―石田梅岩という思想家の価値を捉え直す(石田梅岩の登場;人間にとっての「形」―梅岩の思想の核心 ほか)
第3章 石田梅岩から石門心学へ―日本資本主義の精神の形成に及ぼされた影響力(広がる石門心学;石門心学の中核)
第4章 渋沢栄一と「仕事の思想」―日本近代の創造者が「繋いだ」ものとは何か(江戸の精神と渋沢;渋沢の「仕事の思想」とその精神)
著者等紹介
森田健司[モリタケンジ]
1974年兵庫県生まれ。京都大学経済学部卒業。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(人間・環境学)。2017年より、大阪学院大学経済学部教授。専門は江戸時代の社会思想史。石田梅岩、石門心学の専門家として、多数の研究論文がある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
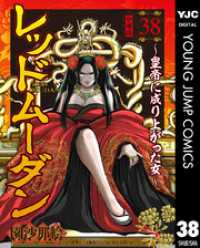
- 電子書籍
- レッドムーダン~皇帝に成り上がった女~…
-
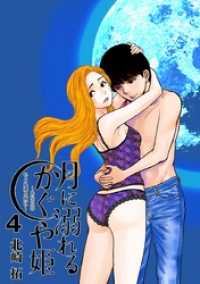
- 電子書籍
- 月に溺れるかぐや姫~あなたのもとへ還る…
-

- 電子書籍
- 節約ロック 分冊版(20)
-
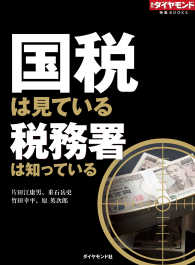
- 電子書籍
- 国税は見ている 税務署は知っている 週…
-
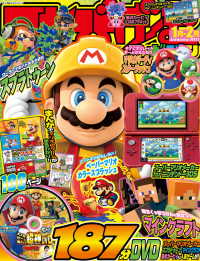
- 電子書籍
- てれびげーむマガジン January …



