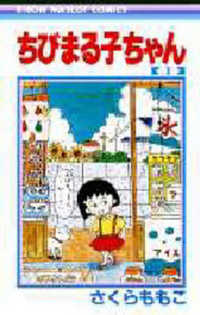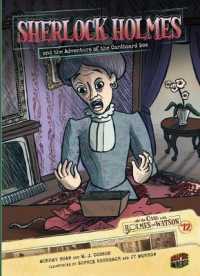出版社内容情報
ナイジェリアには、中国人の酋長が何人もいる。例えば中国国有企業の現地支社に勤める27歳の李満虎は、現地の権力者からの要望で突然地元部族の酋長になった。ナイジェリアと中国との関係が濃密であることの証左といえよう。
中国に親しみを持つ国は、他にもセルビア、エチオピアなど多数存在する。だがその一方、中国ではなく台湾と国交を結ぶカリブ海の小国など、中国に対抗する姿勢を貫く国もある。本書は大国と相対する12か国のリアルを活写。京都精華大学学長ウスビ・サコ氏、「職業はドイツ人」コラムニストのマライ・メントライン氏との対談、さらに孔子学院への潜入記も収録。
【内容例】
vs.イスラエル――サイバー外交に水を差す「開封のユダヤ人」問題/vs.カザフスタン――「一帯一路のスタート地点」が直面する新疆問題/vs.オーストラリア――スパイとコロナ禍で「蜜月」から「対立」へ/vs.カナダ――中国が民主主義社会をハックする/
vs.スリナム――客家と秘密結社と華人大統領etc.
内容説明
ナイジェリアには、中国人の酋長が何人もいる。例えば中国国有企業の現地支社に勤める27歳の李満虎は、現地の権力者からの要望で突然地元部族の酋長になった。同国と中国との関係が濃密であることの証左といえよう。中国に親しみを持つ国は、他にもセルビア、エチオピアなど多数存在する。だがその一方、中国ではなく台湾と国交を結ぶカリブ海の小国など、中国に対抗する姿勢を貫く国もある。本書は大国と相対する12か国のリアルを活写。京都精華大学学長ウスビ・サコ氏、「職業はドイツ人」マライ・メントライン氏との対談、さらに孔子学院への潜入記も収録。
目次
第1章 vs.イスラエル―サイバー外交に水を差す「開封のユダヤ人」問題
第2章 vs.ナイジェリア―差別と利権と「中国人酋長」
第3章 vs.カザフスタン―「一帯一路のスタート地点」が直面する新疆問題
第4章 vS.エチオピア―「中国寄り」WHO事務局長と借金鉄道
第5章 vs.オーストラリア―スパイとコロナ禍で「蜜月」から「対立」へ
第6章 vs.セントビンセント及びグレナディーン諸島―「市議会」レベルの国会をめぐる中台対立
第7章 vs.セルビア―類は友を呼ぶ?相互補完関係が成立
第8章 vs.カナダ―中国が民主主義社会をハックする
第9章 vs.パキスタン―カシミールと核開発で結ばれる「鉄桿朋友」
第10章 vs.スリナム―客家と秘密結社と華人大統領
著者等紹介
安田峰俊[ヤスダミネトシ]
1982年滋賀県生まれ。ルポライター。立命館大学人文科学研究所客員協力研究員。広島大学大学院文学研究科博士前期課程修了(中国近現代史)。『八九六四 「天安門事件」は再び起きるか』(KADOKAWA)で城山三郎賞、大宅壮一ノンフィクション賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
まると
サケ太
Toska
Hatann
-
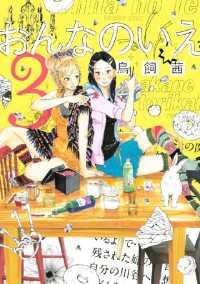
- 電子書籍
- おんなのいえ(3)