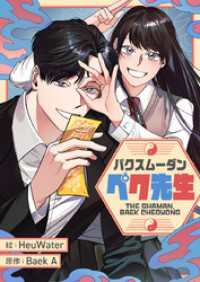出版社内容情報
刀身の煌めきに美を見い出し、「生きる力」をもらう……。不可能とされてきた鎌倉期の名刀の再現を成し遂げた刀匠が語る日本の凄さ。
松田次泰[マツダツグヤス]
刀匠
内容説明
日本刀の世界では、鎌倉期の刀が最高のものとされてきたが、製法が失われ、再現が不可能となっていた。特に江戸期以降、無数の刀鍛冶が再現に挑むも、叶わなかったのである。しかし著者は、遂にその再現に成功した。「名刀」の域に達するのは、並大抵のことではない。名刀であるためには、「品格」が求められる。刀の原料となる和鉄の性質にも通じなくてはならないし、刀の歴史や文化の深い部分も知らなくてはならない。しかし、それがわかったとき、日本文化の美、強さ、精神性の凄さが見えてくる―。希代の実力派刀匠が語る日本刀の真実と、日本文化の真髄。
目次
第1章 日本文化と日本刀―刀は「生きる力」をもらうもの
第2章 鎌倉時代の古刀を再現する―私の刀工修行
第3章 日本刀の歴史とつくり方―珠玉の刀の秘密に迫る
第4章 「至高の美」と「強さ」をいかにつくりだすか
第5章 精神性―神道と産霊
附章 日本刀の見方、愉しみ方
著者等紹介
松田次泰[マツダツグヤス]
昭和23年、北海道北見市生まれ。昭和47年、北海道教育大学特設美術科卒業。昭和49年、刀匠高橋次平師に入門。昭和55年、作刀承認許可。平成8年、日本美術刀剣保存協会会長賞受賞(以後、特賞8回)。平成17年、文化庁長官賞受賞。平成18年、高松宮記念賞受賞。平成21年、無鑑査認定。平成27年、千葉県無形文化財の保持者に認定される(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
双海(ふたみ)
ようはん
活字スキー
文章で飯を食う
のれん