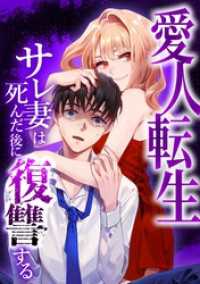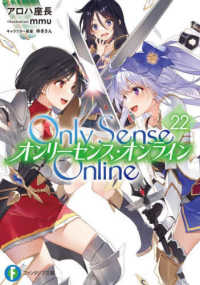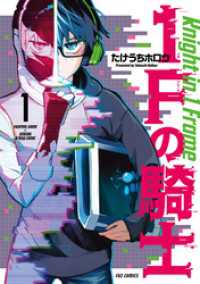出版社内容情報
新聞・雑誌・書籍は何をどう読むか? インターネットで情報を集めるときの注意点は? “池上流”情報収集・整理・解釈・発信術を大公開!
池上彰[イケガミアキラ]
ジャーナリスト
内容説明
テレビ番組のニュース解説、新聞・雑誌連載や書籍の執筆、大学での講義…多方面で活躍し、超多忙な著者。自宅に届く新聞7紙の読み方から、記事のスクラップ法、本の探し方、ネット情報との接し方、話の聞き出し方、わかりやすい説明のコツまで、その情報収集・整理・活用術を一挙公開。「情報の海」で溺れることなく、情報を自らの糧にするためのヒント満載。
目次
序章 情報活用力をいかに高めるか
第1章 私の情報収集術
第2章 私の取材・インタビュー術
第3章 私の情報整理術
第4章 私の読書術
第5章 私のニュースの読み解き方
第6章 私の情報発信術
著者等紹介
池上彰[イケガミアキラ]
ジャーナリスト、名城大学教授、東京工業大学特命教授。1950年、長野県生まれ。慶應義塾大学卒業後、73年NHK入局。報道記者として、松江放送局、呉通信部を経て東京の報道局社会部へ。警視庁、気象庁、文部省、宮内庁などを担当。94年より11年間、『週刊こどもニュース』でお父さん役を務め、わかりやすい解説が話題に。2005年にNHKを退社し、現在はフリーのジャーナリストとして多方面で活躍中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
岡本
76
テレビ、新聞、インターネットと情報が溢れる現代で情報に溺れてしまっている人に向けた一冊。相変わらず読みやすい文章で著者の情報収集術から整理・活用術を纏めた今作。しかし読み進めていく途中で頭を過るのは冠番組で起きた嘘インタビューなどの問題点の数々。注目されてボロが出るようになってしまったのか、構成に関わっていないのか。選挙番組の鋭い質問はともかく、他の番組はこどもニュースの時と比べて雑になっている様に感じてしまうのが何とも。2016/10/18
ゼロ
75
情報を活かすにはインプットの精度を上げ、アウトプットを意識していくこと。結論としてはベタではあるが、週間こどもニュースを筆頭に視聴者に分かりやすく、ニュースを解説している氏だからこそ説得力がある。内容としても、メディアを「健全な懐疑心」を持って見ようというのが腑に落ちた。そもそも新聞も各紙により、情報が違う。朝刊と夕刊では、国外での情報量も違う。国連の表記ですら、誤訳をして使っている。全てをそのまま受け入れることの危険性を説いているのは流石。読書術や新聞のスクラップは、アナログよりだが使えるところも多い。2017/11/22
Rie【顔姫 ξ(✿ ❛‿❛)ξ】
38
インターネットは確かに便利で、今やなしでは生きていけないくらいだけれど、一方で多すぎる情報がかえってアタマを混乱させている。「池上先生」の切り抜きの整理法、私も同じようにやってるのに、ファイルに入れたままで上手く活かせていないなぁ。この本で感じたのは、もう少しアウトプットを増やさなければいけないこと、そして情報を伝えるときに謙虚でなければならないこと。本当に必要なのは、この本で学んだことを、活かすこと。2016/09/10
薦渕雅春
31
2016年の夏の刊行だが、元は2004年に刊行された本の内容を一新して新書として再構成したもとの事。著者がNHKの記者をされてた頃や、『週刊こどもニュース』のキャスターをされてた頃の経験がベースとしてあるようだ。「アウトプットを意識してインプットする」こと、言い方を変えると「誰かに説明するつもりで情報収集する」ということだと。そうする事で自分の頭の中で整理されて身になるものだと。〈自分の考え方に合わない意見〉にこそ目を通す、とも言っている。〈問題意識〉を持っていると、情報は向こうから飛び込んでくる、とも!2019/03/07
みやけん
27
★★★☆☆新聞の読み方等は以前に他の本でも書いてあったので読みやすかった。日経ですら毎日読んでる訳ではないし。斎藤美奈子さんの書評ちょっと探してみよう。アウトプットを意識して取材。TPPなどの略称には気を付けることがメディアリテラシーの向上に繋がる。また講演を聞きに行きたいなぁ。こんなところにもコロナの影響ですねぇ。2022/01/06