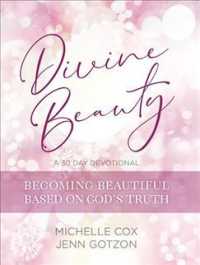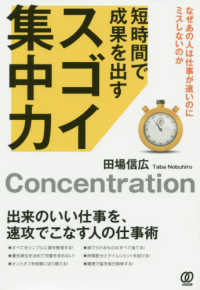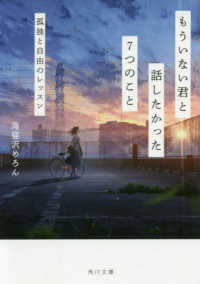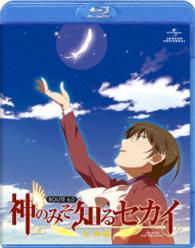出版社内容情報
知的にして軽快、実践的にして洒脱。睡眠時間と社交を確保しながら大量の読み・書きを可能にする、プロフェッショナルのメソッド。
【著者紹介】
文芸評論家、慶應義塾大学環境情報学部教授
内容説明
文筆家が膨大な量のインプットとアウトプットを実現させる技術は、実はビジネスマンに非常に有用だ。仕事の量は減らせない、でも質を下げるのは論外。その厳しい線を突き詰めた著者の「読み・書き」のノウハウは、情報を選りすぐって血肉とし、知的生産へと昇華させるヒントにあふれている。発刊当時「非常に個性的で、かつ実践的」と反響を得た福田和也氏の著作を改訂した本書は、ビジネスマン、読書家、文筆家志望者の必読書である。
目次
第1部 どう読むか(本の「効率的」な読み方;「抜書き」の多様なメリット;本以外の情報の集め方)
第2部 どう書くか(情報整理から表現へ;文章上達の「近道」とは;より幅広く書くために)
著者等紹介
福田和也[フクダカズヤ]
1960年東京生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒業。同大学院修士課程修了。現在、慶應義塾大学環境情報学部教授。93年『日本の家郷』(新潮社)で三島由紀夫賞。『甘美な人生』(新潮社)で平林たい子文学賞、『地ひらく―石原莞爾と昭和の夢』(文藝春秋)で山本七平賞、『悪女の美食術』(講談社)で講談社エッセイ賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
モモのすけ
16
増殖して行く本をどうするか?人それぞれだがこの著者の考え方はしっくりきた。「本質的蔵書」=「精神を活性化させる」ような「感受性のバックボーン」となる本を置くこと。「どう充実させるかが大事なテーマ」2014/02/28
カッパ
13
具体的な方法について書いてあり教えてもらうことができた。特に私にとって心に残った部分として残ったところが3点あった。1点目はそれは手書きでメモをすることの意味について書かれたところである。怠けていたのでよい刺激になった。2点目は新聞を読みいつの朝刊にのっていたと書くこと。スクラップは嫌だったので新たに知れて良かった。3点目は分解して文章を理解するということ。そんなやり方は知らなかったのでびっくりした。2018/10/27
ねこつらら
11
書くための本の選び方、文章上達の方法が書かれたご本でした。文章に対する認識を深めるための、文章の分析方法が面白そうで、一度時間をとってやってみたいなと思わせられました。また、正岡子規さんの考え方である「理想(想像)」は既成のイメージの制約を受けていて、「写生(現実)」のありのままの姿の方が多様多彩だというのが、なるほどにゃ〜という感じで、ちょっと世界観が変わった気がしていますにゃ。2015/07/11
くろまによん
9
かねてからの主張であり、目新しい内容ではなかったが、復習にはなった。この著者の本はなんだか著者と会話しているような気分になる。直接教えを受けているようなね。読んでいて心地いいし、知ってる内容でもより強く認識できるようになるというか、言葉にできないそんな感じ。2015/07/14
緋莢
9
仕事の量は減らせない、でも質を下げるのは論外。ひと月最低100冊は読み、三百枚を書く、その膨大なインプットとアウトプットは、ビジネスマンでも役に立つという著者が明かす「読み・書き」のノウハウ。2015/02/13