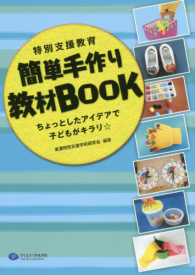出版社内容情報
自民党の憲法草案には96条や9条よりも根本的な問題を孕む改変がある。日本が立憲主義国でなくなる可能性を指摘、憲法の本質を問う。
【著者紹介】
伊藤塾塾長
内容説明
本書はカリスマ塾長の異名をとる著者が、自民党改憲案を検証した上で、憲法の本質を歴史的な観点からわかりやすく解説。96条には民主主義ならではの危険を避ける意図があること、9条が変わるとどうなるかについても言及。
目次
第1章 憲法は「国」を縛るためのルール
第2章 憲法改正のハードルは高い?低い?―九十六条憲法改正
第3章 日本の主権は誰のものか?―憲法前文・天皇
第4章 誰もが生まれながらにして「人権」を持っている―基本的人権
第5章 日本は「戦争をする国」へ?―国防軍の規定
第6章 気になる道州制・外国人地方参政権は?―地方自治
第7章 国家緊急権とは何か―緊急事態
第8章 立憲主義の歴史をたどる
著者等紹介
伊藤真[イトウマコト]
1958年生まれ。弁護士、伊藤塾塾長。東京大学在学中に司法試験に合格。95年に「伊藤真の司法試験塾」(その後「伊藤塾」に改称)を開設、親身な講義と高い合格率で「カリスマ塾長」として人気を博す一方、「憲法の伝導師」として各種集会での講演活動を精力的にこなす。また、弁護士として、「一人一票」の実現のために奮闘中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
-

- 電子書籍
- &フラワー 2024年13号 &フラワー
-
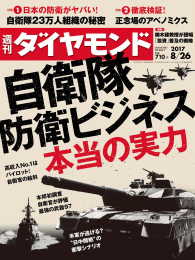
- 電子書籍
- 週刊ダイヤモンド 17年8月26日号 …