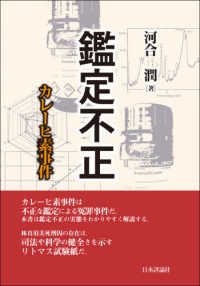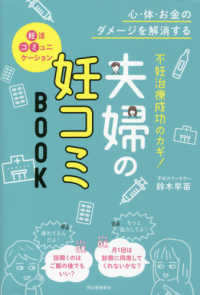出版社内容情報
1人の中学生の自殺が浮き彫りにした「いじめ」の実態。学校は彼を見殺しにしたのか? 社会的問題の口火となった事件を緊急レポート。
内容説明
「自殺の練習をさせられていた」―生徒たちの埋もれかけていた証言から事件は発覚した。いじめと自殺の因果関係を認めず、調査を打ち切った市教委の対応は、社会問題となった。事務作業や保護者対応に忙殺される教師たち。連携さえとれない現状で、はたして子どもの異変を察知することはできるのか。子ども1人に孤独を背負わせる世の中であっていいのか。私たちはいま、彼らのために何ができるのか―。大津支局記者のスクープで疋田桂一郎賞受賞。全国25紙以上に掲載され大反響となった3部にわたる連載記事をもとに、この事件の真相、そして悩ましき、いじめの構造に迫る。
目次
第1章 息子の代弁者になりたい
第2章 先生の感情が見えない
第3章 遺族の真の救いとは
第4章 変わりはじめた教育行政
第5章 同僚性を取り戻せるか
第6章 何がおまえのスイッチなんや
終章 学校だけに委ねない
付録 共同通信が入手した全校生徒アンケートの自由記述欄からの抜粋
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
テンちゃん
101
みんな知っていたはずなのに誰も止められなかった(>_<)彼が自殺しても尚、この世の中からいじめは無くならない(>_<)つい先日も中学2年生の男子生徒が自殺した(。>д<)このままでいいのか学校教育o(`^´*)いじめは現場でおきているのだ!Σ( ̄□ ̄;)毎年いじめで何万という人が亡くなっている(>_<)毎年同じ現状なら何かがおかしいととら得るべき(`へ´*)ノ文科省は真剣にいじめについて考える時がきていると思う(◎-◎;)子どもたちの教育が未来の社会をつくっている!子供だけでなく大人も苦しんでいるのだ😭2015/07/11
サク
60
暴行を受けていた生徒が飛び降り自殺を行った。みんな知っているはずなのに誰も私を助けてくれない『必要のない人間なのか』。いじめを考える絵本『おおきなあな』と共感。暗い闇という心の『あな』に落ちて、誰もかれも憎んだに違いない。見て見ぬふりをしていたものさえも恨んだかもしれない。いじめという体質を改善できる教育力が低下している。学校が、教育委員会が手に負えないほど、子どもたちの心は病んでいる。幼少期からのいじめ教育が家庭、地域、社会で必要とされている。我が子を守るのは親。頼りたい学校の道徳教育の改善を。2015/06/28
鈴
55
親御さんの気持ちを思うと涙なしでは読めず。子供のいじめ自殺があるたびに、死ぬくらいなら転校など方法はいくらでもあったのに、どうして親に相談してくれなかったんだろうとやりきれない思いになる。大人の世界にもいじめはあり、そのいじめている大人も誰かの親だったりで、そんな中で子供からいじめが無くなるわけがない。いじめる側、とくに主犯は誰もがなると限らないが、いじめられる側は誰がなってもおかしくない。息子も来年中学生で他人事ではない。普段から子供の小さな変化に気付けるようにしたい。2017/11/13
mizshnami
41
「いじめかどうかは問題ではなく、相手を傷つける行為そのものが問題である。」この一節に深く頷いた。子供達の関係は学校でつくられるものであり、身近にいる教職員は大きな責任があることを自覚しなければならない。職員の同僚性をいかに築き、保つかは管理職にこそ課せられた課題である。2015/11/21
1.3manen
40
いじめを感知していた教員たち(15頁)の責任。遺族も本人も浮かばれない。学校が信頼をなくすのはいじめ自殺が最たるもの。隠そうとした校長、教委の責任は益々重い。担任の樽井にはネット経由で氏名、住所が明かとなり休職中(16頁)。責任を取らなかったツケ。樽井教諭は国立附属中学から異動となり、ねばならぬ指導が気になったようだ(21頁)。マンモス校(17頁)ではいじめが起きやすいのかもしれない。田舎で少人数教育の方が教育らしいかもしれない。健次は身辺整理できずいじめの対象になりやすかった(42頁)。 2014/12/22
-
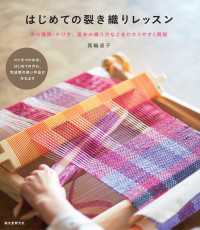
- 電子書籍
- はじめての裂き織りレッスン - 糸の種…