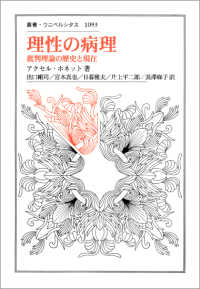出版社内容情報
日本屈指の外交戦略家が解き明かす「外交とは何か」──17世紀ヨーロッパから現在の米中対立まで、日本外交の教訓と指針を示す。
【著者紹介】
元駐タイ大使
内容説明
17世紀ヨーロッパから米中対立まで―日本外交の指針を示す珠玉の外交分析。
目次
近代は終わったのか
バランス・オブ・パワー思想の誕生
むきだしの権力政治
アメリカの登場
帝国衰退の歴史
ウィルソン主義
第二次大戦とは
冷戦とは
平和共存と緊張緩和
泥沼とは
日本にとってアメリカとは
二十一世紀をいかに生き抜くか
著者等紹介
岡崎久彦[オカザキヒサヒコ]
NPO法人岡崎研究所所長。外交評論家。昭和5年(1930)大連生まれ。東京大学法学部在学中に外交官試験に合格し、外務省入省。昭和30年(1955)ケンブリッジ大学経済学部学士および修士課程修了。駐韓国公使、防衛庁国際関係担当参事官を経て、昭和59年(1984)初代情報調査局長に就任。その後、駐サウジアラビア大使、駐タイ大使を務め、平成4年(1992)定年退官。博報堂特別顧問を経て現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ムカルナス
5
米国は特異な国家で民主主義という理想を世界に広めれば平和と繁栄が約束されると信じ自らその宣教師となることを義務付けている国らしい。メイフラワー号の清教徒が建国した国だからなのかキリスト教徒が自らの宗教が唯一無二の正しい宗教と考え世界への布教が人類の為と思っているのと重なる。著者の日米同盟中心論は全く正論で色々勉強になる本だったが米国の絶対的な自己肯定には違和感を感じる。日本は八百万の神々の国なので米国の価値感も受け入れれるが価値観の押売り(しかも実体は国益優先)が世界に摩擦を呼んでいると思う。 2015/12/10
がんぞ
5
外交実務経験もある評論家も八十代、名著とされるキッシンジャー『外交』で数年前与野党議員有志にしたレクチャーの書物化。セオドア・ルーズベルトの国際協調(パワーバランス、現実的選択)とウィルスンの理想主義(それは一般的アメリカ人の心情でもある)に揺れる列強外交。《(日本側の)(必敗の)太平洋戦争になぜ踏み切ったのか(あるいは『追い込まれたのか』)》について幣原喜重郎“日英同盟解消、国際協調期待”が甘かった、山本五十六“米国の国民感情を無視した、奇襲の真珠湾攻撃”で全面的降伏以外の路を閉ざした、の二大失策とする2014/04/12
父帰る
4
二回目の読了。やはり読み落としがかなりあった。岡崎氏が強く指摘した日米同盟の強化を安倍首相は集団的自衛権の法制化で実現した。今その成果をいくら評価しても評価し過ぎることはないだろう。安倍首相が掲げる戦後レジュームからの脱却は、後残すところ憲法改正で達成されると岡崎氏は述べる。これでこの先20年は日本の安全は保障はされると。日本にとって、これからの国際政治は中国を相手にして、厳しい局面を迎えることも予想されている。この本は日本の安全保障の将来を見据える為の必読の書だ。2015/12/07
父帰る
3
キッシンジャーの著書『外交』を引用かつ批評しながら、国際政治の観点から世界史を俯瞰。特にアメリカが国際政治の舞台に登場してからの日米関係の足跡を辿る。私が一番関心を持ったのは、日米開戦の遠因を作った人と戦術的に大きなミスを犯した人の日本側の人物を二人挙げているところだ。その内の一人に就いては、私も以前からそう思っていた。安倍首相のアドバイザーとして岡崎氏は最後に日本が二十一世紀を生き抜く為の貴重な提言を語ってる。本書には、日本国民が安全と自由と繁栄を今後維持するための知恵が凝縮されている。2015/11/23
Mitz
3
キッシンジャーの『外交』を多く引用しながら、近代以降の国際政治史の数々の事象(帝国、ウィルソン主義、第二次大戦、冷戦etc.)を説く。単なる解説・分析ではなく、著者の視線はあくまで21世紀という、これから我々が向き合う時代に向けられており、「『21世紀をいかに生き抜くか』を考えることはすなわち対中国政策を意識しながら米国との関係を考えることだ」という軸が全編を貫いている。自分が何を知り何を考えても何もならないかもしれないけど、一日本人として、歴史的な視座、地政学的な視座を少しずつ養っていきたいと思った。2012/07/30