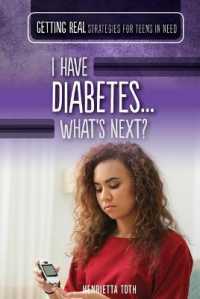出版社内容情報
日本古来の年中行事から、日常の習慣まで、その由来と正しい作法を図解と写真で詳しく解説。日本人なら常識として知っておきたい一冊。
【著者紹介】
宗教研究家
内容説明
風呂敷は文字通り風呂場で使うものだった。四季の移り変わりと人との絆のなかで先人たちが育んできたしきたり。その由来を知れば、自ずと儀式や作法、年中行事への親近感もわいてくる。今こそ見直したい日本のこころ。
目次
第1章 隣近所とのお付き合いにみるしきたり(お辞儀―頭を下げることが、なぜ挨拶になるのか;上座・下座―今も席順のマナーに根強く残るしきたり ほか)
第2章 縁起にみるしきたり(ハレ・ケ―祝いや祭事に着る服をなぜ「晴れ着」というのか;大安・仏滅―吉兆を占う大安と仏滅のルーツ ほか)
第3章 年中行事にみるしきたり(二十四節気―昔の人は、節気をどのように用いたのか;恵比寿講―なぜ七福神のなかで恵比寿さんだけを祝うのか ほか)
第4章 慶弔の儀式にみるしきたり(帯祝い―腹帯を巻く日が、戌の日であるワケ;お宮参り―神前で赤ちゃんをわざわざ泣かせるのには意味がある ほか)
著者等紹介
永田美穂[ナガタミホ]
中国・上海生まれ。日本経済新聞社(月刊誌編集)勤務後、仏教誌の編集主幹などを歴任しつつ、NHKや民放各局のテレビでも活躍。日蓮宗新聞社・編集委員やNHK学園「仏典講座」などの講師を経て、現在は執筆・講演に専心(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おいしゃん
29
一つ一つのモノや仕草に、古来からの意味があるんだなぁと、驚きの連続。こういう風習はぜひ残していきたい。2019/09/06
和草(にこぐさ)
11
それぞれの行事、慣わしには意味や由来がある。それを知ることができた。四季の行事や数字に纏わる話しが書いてあり、さらっと読了。2014/10/21
さわこ
9
日本の良さ、温かみを感じられる一冊でした。日本に住んでいるのに知らなかったこともたくさんあって、もっと自国のことを知らなきゃと思った。関心の低い日本人よりも、日本大好きな外国人の方が日本のことを知っている、みたいなのが結構あると感じるんだけど、それってやっぱり少しさびしいなって。イラスト付きで短くわかりやすくまとめられており、読みやすかった。★★★★★2015/01/31
TERu☆
7
言われてみれは、確かにそうやってるわ!っと思う習慣ばかり。座布団を二つおりにして持ってきて広げるなんてのは、特にそう、そう、と思った。2015/01/14
Humbaba
6
しきたりというのは,もともと意味があったものもあれば,特に意味はなかったが,続けられることによってしきたりとなったものもある.しかし,始まりがどうであれ,しきたりとなっている以上は意味があり,守るほうが良いだろう.2012/04/20
-

- 電子書籍
- アルタスの東風【タテヨミ】第91話 恋…
-

- 和書
- 結婚という決意