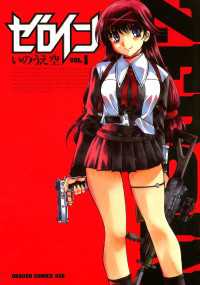内容説明
戦後日本の思想界をリードし、いまなお多大な影響を与えつづけている吉本隆明と柄谷行人の思想を読み解く。二人は互いに真っ向から批判を応酬していたが、思索の領域は驚くほど通底し、重なり合っていたのではないか。個とは何か、意味とは何か、システムとは何か―吉本の三大著作『言語にとって美とはなにか』『共同幻想論』『心的現象論』を読み解き、『隠喩としての建築』『探究1・2』『トランスクリティーク』などから柄谷行人の試みを丹念に追う。いまなお仰ぎ見られる現代思想の可能性、限界に迫る。
目次
第1章 思考の地殻変動(集合論パラドクス;ウエットな構造 ほか)
第2章 個体とは何か(個人と社会;生命・原生的疎外・幻想 ほか)
第3章 意味とは何か(言語における意味と価値;見誤られたソシュール? ほか)
第4章 システムとは何か(「共同幻想」批判の星座;『共同幻想論』は何を語っているのか ほか)
終章 倫理とは何か―愛も正義もないところで(不可欠だが不可能な倫理;関係の絶対性―『マチウ書試論』 ほか)
著者等紹介
合田正人[ゴウダマサト]
1957年香川県生まれ。一橋大学社会学部卒業、東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程中退。琉球大学専任講師、東京都立大学人文学部助教授を経て、明治大学文学部教授。専攻は19、20世紀フランス・ドイツ思想史、ユダヤ思想史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
34
11
合田さんスピノザ好きそうだよね不思議。2019/03/31
しゅん
9
二人の関係の見取り図を得たくて読んでみたら、著者自身の思想が強く表れた一冊だった。遠山啓の数学に影響を受けて「化学と詩」の問題にぶつかった吉本。言い換えればそれは、全ては関係(=化学)でしかない時に、個人(=詩)とは一体なんなのかという問いだろう。柄谷も似た問題を考えており、むしろ彼は吉本より「個人」に拘りがある。それ以上の論旨は明確にできていないが、どうにも苦手意識が先行する二人の言論人に対する新たな捉え方が芽生えたようには思う。柄谷がサルトル的というのは初めて聞いた説。2021/04/25
はすのこ
9
良書。新書の割には読み応えあります。この二人はいつか研究しないとですねぇ。2016/03/23
うえ
7
「アランはサルトルたちの先生の一人である…吉本がつねに意識し続けてきたシモーヌ・ヴェイユもその教え子の一人である。わが小林秀雄もアランの圧倒的影響のもとにその「文体」を作り上げたと思われる。そのアランは…「道徳、それは富者たちのためのものだ。冗談でこう言っているのではない。貧者の生活は出来事が目白押しだ。そこには…ある種の美徳は不可能だ。だから私は、慈善家が貧乏人に与えるよき助言なるものを憎むのである」と断じる。説教を垂れてはならない。そんな時間があれば、汚れた者の体を洗い、もしできるなら…衣服を与えよ」2017/03/20
ポカホンタス
4
仲間と話していてふと吉本隆明が気になった。昔少しかじっただけだったが、私よりも上の世代の左翼系のインテリにとってはヒーローのような存在だったはず。だけど私の周りに吉本隆明を熱く語る人は誰一人いない。結局吉本隆明って何者だったのか。最近は批判的論評が目立っている。いろいろと本が出ている中、これを選んでみた。著者が合田さんであるという点が不安だった。案の定、哲学の専門家でないとわからないような言説がとどめなく溢れていた。(続く)2013/03/17





![神様はじめました 〈第23巻〉 [特装版コミック] (OAD付き限定版)](../images/goods/ar2/web/imgdata2/45921/4592105095.jpg)