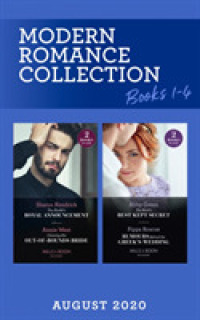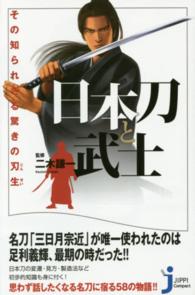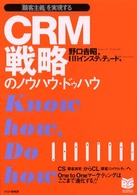内容説明
戦略思考・論理思考・分析思考・クリティカル・シンキングetc.すぐに使える、様々な「思考法」のエッセンスが、この1冊で!「物語」で、「考えるコツ」が、自然に身につく。
目次
第1章 チョコレートの新商品について、二人は考え始めた。
第2章 「何をどう考えたらいいか分からないんです」と、彼女は言った。
第3章 「もう少し、戦略的に考えてみようか」と、彼は言った。
第4章 「分析って、何をどうすればいいんですか?」と、彼女は言った。
第5章 「直感こそ、日ごろの積み重ねなのよ」と、その人は言った。
第6章 「伝えることって、難しいよね」と、彼は言った。
第7章 「考えるの、やめた」と、最後に彼は言った。
著者等紹介
長沢朋哉[ナガサワトモヤ]
1965年、宮城県仙台市生まれ。早稲田大学第一文学部出身。現在、電通ヤング・アンド・ルビカム株式会社に勤務。ストラテジック・プランニング/マーケティング・プランニング部門において、マーケティング戦略、ブランド戦略、コミュニケーション戦略、広告戦略など、広範な領域の戦略立案と実施案の開発に従事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ハッシー
103
★★★★☆ 数ある思考法のエッセンスを物語形式で説明したビジネス書だが、この物語が秀逸。これまで読んだビジネス書で、一番良くできた物語だったと思う。思考法が実際にビジネスシーンでどのように使われるのかを伝えるというメインの軸はしっかりと踏まえた上で、主人公二人の成長や、恋愛を織り交ぜた物語は読んでいて楽しかったし、抗疲労のチョコレートという商品の企画自体が素晴らしいアイデアだと感じた。読み物としても、思考法を学ぶという意味でもオススメの一冊。2019/02/18
コージー
59
★★★★☆問題解決のフレームワークをわかりやすくまとめたもの。製菓メーカーでの新商品立案をストーリー形式にしたものと、解説の2部構成。筆者があらゆる書を咀嚼したというだけあって、とてもわかりやすい。イシュー、MECE、3C、STP、4Pなど、王道をさらえる内容ともいえる。【印象的な言葉】①「伝える」ことは手段であって、「意思決定・行動」してもらうことが目的である。②「考える」ことは手段であって、目的は「自分の主張を決めること」③論理的思考のポイントは、「So what?」「Why so?」の2つである。 2018/06/08
こばたく
37
【社会で活躍する人の基礎にある思考の型を学びたいあなたへの一冊。】 ◆要点 批判的思考力、論理的思考力、市場分析、プレゼン力… あなたはこれらの要点を簡潔に説明できますか?本書はデキる社会人の基礎にある思考の型を網羅的に解説している。本書の1番の特徴は物語形式の点で、型を学ぶ若手Aと、型を教える上司Bの両役になりきって楽しく読み進められる。 ◆感想 思考の型について、上っ面の理解止まりで実務に落とし込めていないと気付かされた。社会人の基礎力が網羅的にサクサク読めるので、繰り返し読んで染み込ませたい。2021/04/05
Kentaro
24
目的と手段という概念は、思考のフレームワークとして位置づけてよい。考えるという行為は、手段にあたる。よって、そこにはなんらかの目的がある。その考えることの目的について、物語の中で優人はある事柄についての自分の主張を決めることだと、京子に説明します。考えることの目的は、決めることだということです。では、何を、決めるのか。その何をにあたる部分が分からなくなってしまうから、人は混乱してしまうのです。ですから、優人は「まず、『決めるべきことメニュー』を作って、複数の中から選択・決定しよう」と提案します。2019/02/02
わった
15
もっと物事をきちんと考えられるようになりたいなぁ、でも難しい実用書じゃ実用できないしなぁ、と思っていたところ、世界一やさしいという文字に弾かれて読んでみました。物語形式になっていて、とても実用的で例もあり、わかりやすかったです。それでも難しくて自分の中に落とし込めていない部分は多々あるのですが、本の内容をまとめながら、自分の中に落とし込んで使っていけそうなものもいくつかありそうなので、活かしていきたいと思います。2019/03/08