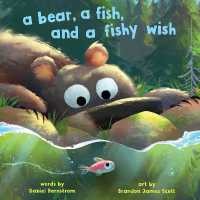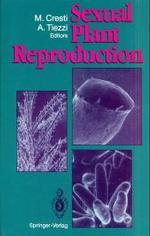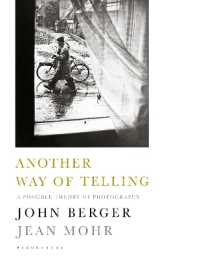出版社内容情報
歌舞伎座誕生の内幕と、松竹独占の背景を探る。
歌舞伎座が建て替えられようとしている。明治22年に開場した歌舞伎座誕生の秘話と、松竹の傘下に入るまでの経緯を丹念に描く。
歌舞伎座が建て替えられようとしている。現在の地に歌舞伎座という劇場が開場したのは一八八八年(明治二十二年)、憲法発布の年である。現在の歌舞伎座は松竹直営の劇場だが、この時点では松竹はまだない――。いったい、歌舞伎座はいかに誕生したのか? そして、なぜ松竹のものになったのか? 本書は膨大な資料から丹念に読み解いた、明治の劇壇を舞台に織りなされた人間模様の実録である。歌舞伎ファン必読の一冊!
▼目次:江戸の終焉/それぞれの維新(明治二年~十二年)/活歴と自由民権運動(明治十三年~十五年)/演劇改良会と天覧劇(明治十六年~二十年)/歌舞伎座開場(明治二十一年~二十三年)/迷走する歌舞伎座(明治二十三年~二十八年)/旧世代の退場と新世代の台頭(明治二十九年~三十六年)/ポスト團菊(明治三十六年~四十一年)/松竹東征と田村大将軍(明治四十二年~大正二年)
●歌舞伎座はいつから松竹のものになったのか ――まえがきにかえて
●第一章 江戸の終焉
●第二章 それぞれの維新 明治二年(1869)~十二年(1879)
●第三章 活歴と自由民権運動 明治十三年(1880)~十五年(1882)
●第四章 演劇改良会と天覧劇 明治十六年(1883)~二十年(1887)
●第五章 歌舞伎座開場 明治二十一年(1888)~二十三年(1890)
●第六章 迷走する歌舞伎座 明治二十三年(1890)~二十八年(1895)
●第七章 旧世代の退場と新世代の台頭 明治二十九年(1896)~三十六年(1903)
●第八章 ポスト團菊 明治三十六年(1903)~四十一年(1908)
●第九章 松竹東征と田村大将軍 明治四十二年(1909)~大正二年(1913)
●参考文献
内容説明
歌舞伎座はいかに誕生したのか?そして、なぜ松竹のものになったのか?明治の劇壇を舞台に織りなされた人間模様の実録!江戸から明治へ―歌舞伎の世界に何が起こったのか。
目次
第1章 江戸の終焉
第2章 それぞれの維新―明治二年(一八六九)~十二年(一八七九)
第3章 活歴と自由民権運動―明治十三年(一八八〇)~十五年(一八八二)
第4章 演劇改良会と天覧劇―明治十六年(一八八三)~二十年(一八八七)
第5章 歌舞伎座開場―明治二十一年(一八八八)~二十三年(一八九〇)
第6章 迷走する歌舞伎座―明治二十三年(一八九〇)~二十八年(一八九五)
第7章 旧世代の退場と新世代の台頭―明治二十九年(一八九六)~三十六年(一九〇三)
第8章 ポスト團菊―明治三十六年(一九〇三)~四十一年(一九〇八)
第9章 松竹東征と田村大将軍―明治四十二年(一九〇九)~大正二年(一九一三)
著者等紹介
中川右介[ナカガワユウスケ]
1960年生まれ。早稲田大学第二文学部卒業。カメラ雑誌編集長を経て、現在「クラシックジャーナル」編集長。出版社「アルファベータ」代表取締役として、海外の偉大な音楽家・文学者の評伝などの翻訳書を多数出版する。また自らもクラシック、歌舞伎、日本歌謡界などに精通し、その関連書を精力的に執筆(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
sawa
みつひめ
Motonari