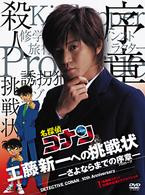- ホーム
- > 和書
- > 新書・選書
- > 教養
- > PHPサイエンスワールド新書
出版社内容情報
数学の2千年の歩みを、広い視野から眺める。
数学とはどういう学問か。古代ギリシアから現代まで、数学の2000年以上に及ぶ歩みを人間精神の足跡として広い視野から眺める。
数学者たちの心の声を聴け! 2000年有余の「数学の歴史」を眺望する。
▼数学が時間の問題と出会ったとき、数学から時間が消えたとき、数学が無限の「亡霊」と出会ったとき……数学と哲学は最も長い歴史をもつ学問という。数学とはいかなる精神の下で誕生したのか。数学者たちはいったい何を追い求めてきたのだろう。古代ギリシア人が円周率πや√2といった数の神秘に出会ったときの驚きと衝撃は、いかほどのものであったのか。またそれは、後世にいかに引き継がれたのか。
▼デカルト、オイラー、ニュートン、ライプニッツといった多彩な顔ぶれは、数学が直面する無限や時間の問題といかに格闘したのか。「数学の歴史」を、人間精神の歩みとして、その足跡を辿っていく。
内容説明
数学とはいかなる精神の下で誕生したのか。数学者たちはいったい何を追い求めてきたのか。古代ギリシア人が円周率πやルート2といった数の神秘に出会ったときの驚きと衝撃は、いかほどのものであったか。またそれは、後世にいかに引き継がれたのか。デカルト、オイラー、ニュートン、ライプニッツといった多彩な顔ぶれは、数学が直面する無限や時間の問題といかに格闘したのか。2000年有余の数学の歴史を、人間精神の歩みとして、その足跡を辿っていく。
目次
序章 聞いてみたいこと
第1章 深い森へ
第2章 近世に向けての旅立ち―文明の流れのなかで
第3章 ヨーロッパ数学の出発
第4章 数学の展開
第5章 関数概念の登場
第6章 解析学の展開
著者等紹介
志賀浩二[シガコウジ]
1930年新潟市生まれ。東京大学大学院数学系修士課程を修了。東京工業大学名誉教授。「数学の啓蒙」に目覚め、精力的に数学書を執筆している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
翔亀
マルレラ
ちくわん
ごま
pyonko
-
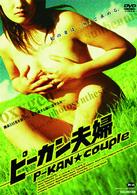
- DVD
- ピーカン夫婦