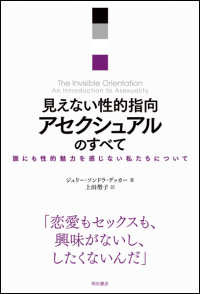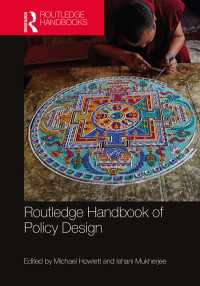出版社内容情報
将棋界の偉人、大山康晴の勝負観とは何か。
将棋界の偉人、大山康晴。「忍」をモットーとして、「七転八倒」を座右の銘とした勝負師の人生観は今なお輝き続ける。昭和の名著を復刊。
羽生善治氏推薦。
▼「勝負の世界に必要不可欠なものがここにある」
▼
▼勝負の世界では、自分だけが頼りである。
▼それは将棋に限らず、すべての職業についてもいえることだ。
▼その頼りになる自分を鍛え上げていくのが、プロになる条件であり、勝ち続けるための条件である。
▼昭和を代表する棋士は、勝ち続けるために何を考え、実行してきたのか?
▼勝ち続けるための極意を説いた永遠の名著。先行き不透明な現代にこそ、その真価は発揮されるはずである。
[1]名局のこころ
[2]助からないと思っても助かっている
[3]こころの姿勢を正せ
[4]肩書きより実力を
[5]ムダな労力を惜しむな
[6]楽観ムードは赤信号
[7]ライバルを持て
[8]幻の自分の騙されるな
[9]まず結論を出せ
[10]おのれに克つ
[11]棒ほど望めば針ほど叶う
[12]楽天家であれ
[13]つきを大事にせよ
[14]切り捨てが大切
[15]何でも仕事に結びつけよ
[16]連係プレーを大切にせよ
[17]最大の敵は味方の駒
[18]駒の配置に気をくばれ
[19]序盤で戦いは始まっている
[20]常に未知の世界へ挑戦せよ
[21]プロは自分だけが頼り
[22]勝つことが最善の健康法
[23]人の言葉には耳を傾けよ
[24]マンネリズムを避けよ
[25]一日に一分でもいいから反省せよ
[26]負けないコツがある
[27]道具も芸のうち
[28]スランプ退治の必勝法
[29]飛びこんで苦労を求めよ
[30]貯金で生活するな
[31]得意業を過大評価するな
[32]戦う前には細心の注意を
[33]好条件は自分で作り出せ
[34]外形でなくこころを学べ
[35]自分一人では大成しない
[36]決断は見通し七割で
[37]ローマは一日にしてならず
[38]教えることは学ぶこと
[39]対局は常にマイペースで
[40]合理化には落し穴がある
[41]読み筋に入ったときは警戒せよ
[42]一局で三回は形勢判断を
[43]良い手を指そうとするな
[44]技術だけでは勝てない
[45]勝つよりも負けないことを
[46]年々歳々人同じからず
[47]失意の時期は休暇と思え
[48]過去の照り返しに生きるな
[49]ときには自分に重荷を課せよ
[50]受けとは攻めることである
[51]慎重すぎて悪いことはない
[52]マラソン競争でいこう
[53]初めのチャンスは見送れ
[54]肩の力を抜いて投球せよ
[55]勝負は日常心にあり
[56]山勘に頼るな
[57]記録は作られるものである
[58]自分で自分を教育せよ
[59]目に見えないものをつかめ
[60]想像力が勝負の鍵
[61]いつでも出直しの道はある
[62]仕事に停年はない
内容説明
勝ち続けるための極意を説いた永遠の名著。
目次
名局のこころ
助からないと思っても助かっている
こころの姿勢を正せ
肩書きより実力を
ムダな労力を惜しむな
楽観ムードは赤信号
ライバルを持て
幻の自分に騙されるな
まず結論を出せ
おのれに克つ〔ほか〕
著者等紹介
大山康晴[オオヤマヤスハル]
1923年岡山県に生まれる。幼少より将棋に親しみ、35年、12歳で大阪の木見九段の門下となる。48年、25歳で八段、52年、第11期名人戦で木村名人を破り名人位を獲得。以後、連続5期名人保持により、15世名人の資格を得る。他に永世10段・永世王将・永世棋聖。優勝124回。獲得タイトルは、名人18を初め80期。A級(名人含む)在位45年。NHK放送文化賞、紫綬褒章、東京都文化賞、菊池寛賞、文化功労者、正四位勲二等瑞宝章などの栄誉に浴する。92年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
糜竺(びじく)
macho
kenitirokikuti
geki
ピンクのまぬけ