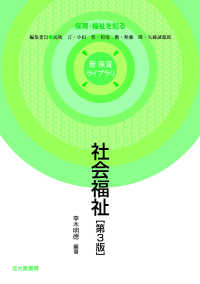- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
出版社内容情報
サケ、サクラなどヤマトコトバに謎を解く鍵が。
日本の花といえば桜。桜といえば花見。花見といえば酒。なぜ、日本人はサクラの木の下でサケを飲むのか? 謎を解く鍵は「サ」にある。
日本の国花といえば昔からサクラ(桜)。
▼日本の伝統的な飲みものといえばおサケ(酒)。
▼
▼春を迎えて、サクラの花が美しく咲き乱れると、日本人の多くは、家族や同僚、友人たちとサクラの木の下で、お弁当をひらき、おサケを飲み、挙句の果ては、歌ったり踊ったりしだす人々があらわれます。こうしたお花見の風景は日本では永らく繰り返されている年中行事のような慣習です。
▼しかし、アメリカでは日本から移植したサクラの花が咲き、散策の人々で賑わってもサクラの木の下で宴をひらく風習はないようです。
▼なぜ、日本人はサクラの花を見るとおサケが欲しくなったり、浮かれたくなったりするのでしょうか?
▼サクラにしてもおサケにしても、どちらの言葉にも「サ」の字がついていますが、この「サ」が問題を解く鍵になるのです。
▼本書では、「サ音」の神聖視をてがかりに、日本民族のアイデンティティーを探り、お花見の起源を解明していきます。
[I]
●神様の名が地名に
●サ神は山の神
●山の神から田の神へ
●山の神楽
●サイバラ(催馬楽)
●サは神聖な音(おん)
●神の判断
●日本の国家サクラ
●サイグサさん
[II]
●サ神とネンギ
●サ神の痕跡と進化
●中世におけるサイノ神
●サイノカミ祭の一例
●古典に残る粥杖(かゆ)
●鵜坂神社の尻打祭
●尻たたき棒
●カユかき棒
●外国における人畜打撲の風習
●「さったち」と熊祭り
[III]
●サ神はどこで生まれたのか
●サスンヤとツカサ
●伝説の伝播 ――ウサギとワニの物語
●大黒様の話
内容説明
「サ音」の神聖視を手がかりに日本民俗のアイデンティティーを探りお花見の起源を解明していく。
目次
1(神様の名が地名に;サ神は山の神;山の神から田の神へ ほか)
2(サ神とネンギ;サ神の痕跡と進化;中世におけるサイノ神 ほか)
3(サ神はどこで生まれたのか;サスンヤとツカサ;伝説の伝播―ウサギとワニの物語 ほか)
著者等紹介
西岡秀雄[ニシオカヒデオ]
大正2年(1913)、仙台生まれ。昭和41年(1939)、慶應義塾大学文学部史学科卒業。慶應義塾大学助教授、慶應義塾大学教授を経て、昭和54年(1979)より慶應義塾大学名誉教授。同年、大田区立郷土博物館館長に就任。平成13年(2001)、大田区立郷土博物館館長を退任。現在、日本トイレ協会名誉会長、大森貝塚保存会名誉会長、日本旅行作家協会名誉会員なども務める。専門は考古学・人文地理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 四季 冬 Black Winter 講…