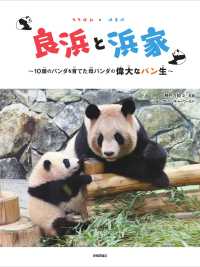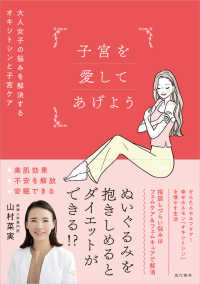出版社内容情報
光源氏と女たちの足跡を訪ねる京都散策の書。
『源氏物語』のあらすじを解説しながら、舞台となった京都御所、嵯峨野、清涼寺、宇治などを訪ね歩く。千年前の情景が甦る歴史散策の書
千年にわたって読みつがれ、今なお人びとの心を揺さぶる『源氏物語』。その主人公、光源氏や女たちが見た平安の都の場景とは――。本書は五十四巻からなる長編のあらすじを丁寧に紹介しながら、ゆかりの寺社、庭園、風物を訪ね歩く。若き源氏が暮らした京都御所をはじめ、空蝉、夕顔、紫の上、玉鬘といった女たちとの逢瀬の場となった五条の宿、東山、北山、嵯峨野へ……。小路から大橋、河畔、山々に至るまで、京都の風光には『物語』の気配が溶け込んでいる。例えば、薄幸の美女、夕顔が住んでいたとされる下京区高辻通堺町下ルには、いまも「夕顔町」という地名が残っている。京都の人々が『物語』のなかの人物とはいえ、夕顔を哀れんで町名にしたり、墓をたてたりしたところに、この物語への愛情を感じる。なんども訪れたことのある京都も、『源氏物語』を読み返すことで歩き方が変わるに違いない。カラー口絵写真も添えながら、王朝絵巻が甦る源氏紀行の決定版である。
●その序 『源氏物語』の場景を訪ねる前に
●第一章 冒頭巻の「桐壺」から「帚木」「空蝉」「夕顔」を読む
●第二章 幼妻をえる「若紫」から失意の「須磨」「明石」までを読む
●第三章 復権の「澪標」から華麗な六条院の巻と「玉鬘十帖」を読む
●第四章 『物語』の白眉「若菜上下」から次世代の巻と源氏の終末を読む
●終章 三世代の巻々と「宇治十帖」の男女を読む
内容説明
千年にわたって読みつがれ、今なお人びとの心を揺さぶる『源氏物語』。その主人公、光源氏や女人たちが見た平安の都の場景とは―。本書は五十四巻からなる長編のあらすじを丁寧に紹介しながら、ゆかりの寺社、庭園、風物を訪ね歩く。若き源氏が暮らした京都御所をはじめ、空蝉、夕顔、紫の上、玉鬘といった女たちとの逢瀬の場となった洛中、東山、北山、嵯峨野の名所へ…。小路から大橋、河畔、山々に至るまで、京都の風光には『物語』の気配が溶け込んでいる。カラー写真も揃え王朝絵巻が甦る源氏紀行の決定版。
目次
『源氏物語』の場景を訪ねる前に
第1章 冒頭巻の「桐壷」から「帚木」「空蝉」「夕顔」を読む(『物語』の時代背景と「京都御所」;若き源氏の恋と「京都御苑」周辺;源氏の女人彷徨と東山山ろくの寺社)
第2章 幼妻をえる「若紫」から失意の「須磨」「明石」までを読む(紫の君の登場と洛北の山寺;危険な情愛に溺れる若き源氏;源氏の光と影を映す洛外の地;『源氏物語』はどのように執筆されたのか;流離生活を余儀なくされる源氏の君)
第3章 復権の「澪標」から華麗な六条院の巻と「玉鬘十帖」を読む(政権に復活して権門家への道を歩む;『物語』の主人公が源氏の次世代に;「玉鬘十帖」にみる源氏の変容;華麗な六条院での愛の暮らし;玉鬘に悩まされる男君と女君)
第4章 『物語』の白眉「若菜上下」から次世代の巻と源氏の終末を読む(『物語』の最長編となる「若菜」の上下巻;「盈つれば虧くる」―たちこめる暗雲;光源氏の長大な物語の終焉)
終章 三世代目の巻々と「宇治十帖」の男女を読む(源氏亡きあと『物語』はなにを描く;宇治十帖と宇治の風光)
著者等紹介
山折哲雄[ヤマオリテツオ]
1931年サンフランシスコ生まれ。東北大学文学部卒。国立歴史民俗博物館教授、京都造形芸術大学大学院長、国際日本文化研究センター所長などを歴任
槇野修[マキノオサム]
1948年東京生まれ。慶應義塾大学文学部卒。朝日新聞社、ダイヤモンド社で雑誌・書籍の編集に携わり、80年に編集工房「離山房」設立。歴史・文芸考証をテーマとし、最近は京都関連の執筆をおこなう(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
sheemer
wang
bittersweet symphony
dzuka