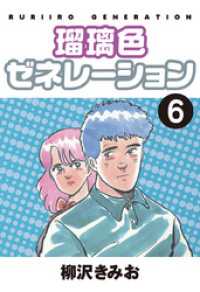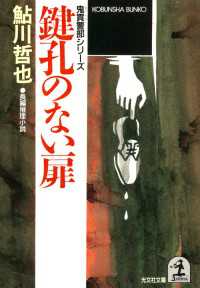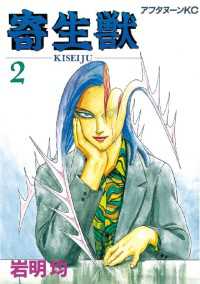出版社内容情報
少女漫画が当時の若者に与えた影響を考察する。
大島弓子と萩尾望都、岡崎京子……少女漫画の名作を読み解きながら、一九七〇年代から現在に至るまでの“純粋少女”の変遷をみる。
一九七〇年代から現在に至るまで、巨大な潮流をつくってきた少女漫画の歴史を、<純粋少女>をキーワードに読み解く。とくに“二十四年組”を中心に花開いた<少女漫画>の魅力とその高度な達成について――大島弓子の『バナナブレッドのプディング』、萩尾望都の『トーマの心臓』、そして岡崎京子の『ヘルタースケルター』を主な手がかりに――戦後文化論として読み解く。少女漫画のヒロインたちが抱える繊細な“怯え”は、大人の論理が強要する安易な成熟の拒否であり、無意識の抵抗だったのではないか。今日に至るまで連綿と受け継がれてきた“震え”や“怯え”の伝達装置としての<純粋少女>たちに、高度消費社会の諸矛盾を、戦後民主主義の限界を乗りこえる可能性をみる。巻末に「少女漫画の名作一覧」を収録。
●序章 七十年代少女漫画前史 ――戦後民主主義と成熟の拒否
●第一章 大島弓子と『バナナブレッドのプディング』
●第二章 純粋少女とは何か?
●第三章 萩尾望都と『トーマの心臓』
●第四章 岡崎京子と『ヘルタースケルター』
●終章 純粋少女と少女漫画のいま
●[巻末付録]少女漫画の名作一覧
内容説明
一九七〇年代から現在に至るまで、とくに“二十四年組”を中心に花開いた“少女漫画”の魅力とその高度な達成―大島弓子と萩尾望都、岡崎京子の作品を主な手がかりに、少女漫画を戦後文化論として読み解く。ヒロインたちが抱える繊細な“怯え”は、大人の論理が強要する安易な成熟の拒否であり、無意識の抵抗だったのではないか。今日に至るまで連綿と受け継がれてきた“震え”や“怯え”の伝達装置としての“純粋少女”たちに、高度消費社会の諸矛盾を乗りこえる可能性をみる。巻末に「少女漫画の名作一覧」を収録。
目次
序章 七〇年代少女漫画前史―戦後民主主義と成熟の拒否
第1章 大島弓子と『バナナブレッドのプディング』
第2章 純粋少女とは何か?
第3章 萩尾望都と『トーマの心臓』
第4章 岡崎京子と『ヘルタースケルター』
終章 純粋少女と少女漫画のいま
巻末付録 少女漫画の名作一覧
著者等紹介
飯沢耕太郎[イイザワコウタロウ]
1954年宮城県生まれ。日本大学芸術学部写真学科卒業。筑波大学大学院芸術学研究科博士課程修了。1990~94年、写真誌『デジャ=ヴュ』編集長を務めるなど、写真評論家として精力的に活動を展開。『写真美術館へようこそ』(講談社現代新書)でサントリー学芸賞、『「芸術写真」とその時代』(筑摩書房)で日本写真協会年度賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
阿部義彦
ぐうぐう
佐島楓
カキ@persicape
wm_09