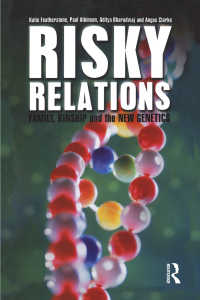出版社内容情報
「封建制」を再評価する文明論的考察の書。
封建制とは近代化の通過儀礼であり、民主主義に至る絶対条件である。西洋、日本、中国の歴史をひもときながら、封建制の再評価を試みる。
封建制は民主制の反対概念として、悪しきものの形容詞にされてきた。しかし、歴史学的に検証すれば正しい評価といえるのだろうか? 十三世紀、蒙古軍の侵略をはね返した日本、西欧、エジプトの三地域では、いずれも封建制が確立していた。中国やペルシアなど、官僚制が行き渡っていた領域、あるいは東欧のように建国ほどなく封建制も緒についていない地域は、たやすく蒙古軍に踏み破られたのだ。また、ルネッサンスや産業資本主義も、極東、西欧、中東という、モンゴルの影響を逃れた地域から発展している。私たちは、封建制なる事象をどう考えてゆけばよいのか。本書では「封建」の歴史的経緯や語源をたどりながら、福沢諭吉、梅棹忠夫、網野善彦、ウィットフォーゲルなどの学説を丹念に検証。第二次大戦後、日本の敗戦は前近代の封建制が充分に克服されていなかったとする進歩的文化人の見解に異議を申し立て、歴史遺産としての封建制に光をあてた真摯な論考である。
●序章 現代日本に受け継がれている封建制
●第一章 モンゴルの世界征服と封建制
●第二章 日本人は封建制をどうみてきたか
●第三章 島崎藤村と大隈重信 ――封建制評価の動き
●第四章 近代日本と封建制
●第五章 梅棹忠夫とウイットフォーゲル
●第六章 その後の封建制論
内容説明
封建制は民主制の反対概念として、悪しきものの形容詞にされてきた。しかし、歴史学的に検証すれば、正しい評価といえるのだろうか?十三世紀、蒙古軍の侵略をはね返した日本、西欧、エジプトでは、いずれも封建制が確立していた。また、近代化、産業資本主義も、封建制が根づいた地域から発展している。私たちは、封建制なる事象をどう考えてゆけばよいのか。福沢諭吉、梅棹忠夫、網野善彦、ウィットフォーゲルなど諸先学の学説を丹念に追いながら、歴史遺産としての封建制に光をあてた真摯な論考。
目次
序章 現代日本に受け継がれている封建制
第1章 モンゴルの世界征服と封建制
第2章 日本人は封建制をどうみてきたか
第3章 島崎藤村と大隈重信―封建制評価の動き
第4章 近代日本と封建制
第5章 梅棹忠夫とウィットフォーゲル
第6章 その後の封建制論
著者等紹介
今谷明[イマタニアキラ]
1942年京都市生まれ。京都大学経済学部卒業後、大蔵省、経済企画庁に勤める。その後、京都大学大学院へ入学し、1976年、同大学院文学研究科博士課程単位取得退学。文学博士。専攻は、日本中世政治史。国立歴史民俗博物館助教授、横浜市立大学教授、国際日本文化研究センター教授などを経て、現在、都留文科大学学長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。