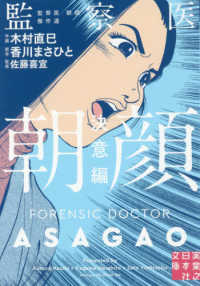- ホーム
- > 和書
- > 文芸
- > 海外文学
- > その他ヨーロッパ文学
内容説明
一七七六年に初巻が発売されるや、たちまち希代の名著としての地位を確立したギボンの『ローマ帝国衰亡史』。その時代の人々の教養の証として「各家庭の食卓、いや、ほとんどすべての化粧台にまでも置かれた」といわれるこの歴史書から、現代人は何を学ぶべきなのか。本書では、原著に記された各時代の代表的な章を選び、上巻(第1章~第7章)において、初代皇帝アウグストゥスの時代から、コンスタンティヌス帝および子息帝らの治世までの歴史を眺望する。
目次
初代皇帝アウグストゥスがあたえた指針
ブリタニアの征服
トラヤヌス帝による版図拡大
内政を充実させた後継者たち
帝威を支えた兵制と軍事力
帝国の属州
寛容な宗教政策
実利的なローマ人
ラテン語の普及とギリシア文化の遺産
ローマ帝国における奴隷たち〔ほか〕
著者等紹介
中倉玄喜[ナカクラゲンキ]
1948年、長崎県平戸市生まれ。高知大学文理学部化学科卒。在日外国大使館、翻訳会社経営、環境英字紙の発行人などを経て、現在ローマ史関係の翻訳を手がける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
イプシロン
35
(再読)さすがに冷静に読める二回目ともなると、皇帝を中心とした記述だけだとさすがに物足りなさを感じた。当時のローマ帝国の国政・軍政といったシステムの周縁部が見えなさすぎて、ただ著者の言葉を素直に受け取る以外になく、なんら検証的な読み込みができなかったからだ。所詮、<普及版>は普及版でしかないのだろう。同様に、巻末にあるキリスト教についての記述も物足りなさを感じた。しかし、それは自分の読書力が上がった証拠であるのかもしれない。2022/10/10
イプシロン
20
五賢帝の時代、ローマ帝国が最も栄えて平穏であった頃ですら人類の抱えてきた問題(奴隷制度)は全く解決されていない。その後につづく血で血を洗う殺しあいを眺めているだけで、軍事力を背後にもつ政治で人類が幸福になることは永久にありえないという思いが一層強まった。また上巻終盤に登場するキリスト教二派(正教・公教)の対立と政治への癒着が帝国の分裂、衰亡への要因となっていくさまを見ると、平和への道はギボンの言う「名称や儀式こそ違え、同じ神々を崇めている」という多神教的“哲学”に人類が目覚めるしかないのだろうと思えた。2018/05/09
Bashlier
20
0/5 酷い翻訳がここまで作品を貶めているのは初めてだ。さらに、誤字脱字や誤変換のチェックなど、編集として最低限のことも為されていない。書籍と呼ぶのはおこがましい単なる文字の集積物である。言葉は丁寧に加工されて初めて価値を持つのだと再認識させられた。妻は大手出版社で編集者として働いているのだが、その仕事の社会的重要性を改めて感じさせてくれたことについて著者に感謝したい。2017/11/11
バズリクソンズ
18
18世紀にこれだけの歴史的証拠を集め、ローマ帝国の起源から滅亡までに迫るのは著者の尽力の賜物であり、現代社会に於いても何ら変わり映えしない事実を伝える。争いの発端は嫉妬、猜疑心から始まり、物欲、金銭欲の強欲へと発展、親族すらも支配のためなら死に至らしめる。この上巻の最後はキリスト教が他の宗教を抑えトップに君臨した経緯も記されており、政治と宗教の結び付きは古代ローマの時代から始まっていた事に関心を抱かずにはいられなかった。各章を終えての訳者による丁寧な解説も読者に良く配慮された作品で駆け足気味に知るには最適2022/12/03
MAT-TUN
9
このような優れた書があったとは。非常に面白い。ローマ皇帝の事績をつづりつつ、蛮族の侵攻やそれに対する対応策などなかなか面白いし、キリスト教に関する記載も興味深い。当時の風景が目に見えるようだ。ときおり現代(18世紀)とも重ね合わせつつ語られる筆の運びに著者の力量が伺える。歴史が立体的に見える。時間と空間を自在に行き来できる力量を持ち合わせたギボンの文章に魅せられる。ぜひみなさんよみましょう。訳も良い。原著のもつ魅力を生かすような翻訳を心がけているように感じられる。2013/07/04
-
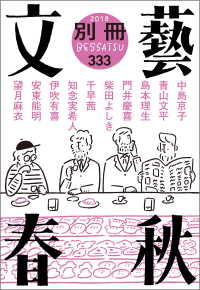
- 電子書籍
- 別冊文藝春秋 電子版17号 文春e-b…
-

- 電子書籍
- 書物袋