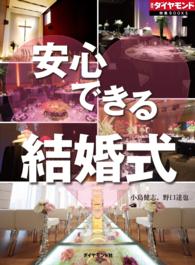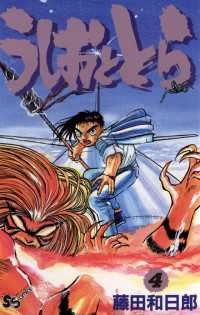内容説明
カレー、焼鳥、トンカツなど、日本人がこよなく愛する味を黙々とつくり続け、暖簾を守る主人たち。戦災を乗り越え、高度経済成長に浮かれることなく、バブル崩壊後も商売を続ける店を支えたのは、変わらぬ味を慈しむ客たちである。本書は、浅草、銀座、神田、日本橋、神楽坂と、昭和の香り漂う老舗を訪ねる味の旅。主人の話と著者自身の思い出が交錯し、「たそがれゆく昭和」が鮮やかに浮かび上がる。前作『明治・大正を食べ歩く』同様、店を通じてひもとく「もう一つの昭和史」。
目次
第1章 浅草
第2章 銀座・有楽町・新橋
第3章 神田・日本橋・神楽坂
第4章 渋谷・赤坂・六本木
第5章 新宿・高田馬場・池袋
第6章 横浜
著者等紹介
森まゆみ[モリマユミ]
1954年、東京都文京区生まれ。作家・地域雑誌編集者。早稲田大学政経学部卒業。1984年、地域雑誌「谷中・根津・千駄木」(愛称・谷根千(ヤネセン))を発刊。主な著書に、『鴎外の坂』(新潮文庫・平成9年度、芸術選奨文部大臣新人賞)、『「即興詩人」のイタリア』(講談社、JTB紀行文学賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やすらぎ
124
東京にある懐かしの老舗を紹介。「土手の伊勢屋」創業明治22年。きつね色にからっと揚げたご飯の見えない名物天丼。「ナイルレストラン」創業昭和24年。ムルギーランチが名物。ようく混ぜてねと店主の一声。「新橋お多幸」創業昭和7年。赤い取り皿に映える名物おでんは芸術。「西村果物店」創業明治43年。上品で滑らかなシャーベット。…本書は旨いものガイドではなく、お店の歴史やお人柄を通じて懐かしの昭和を食べ歩いている。黙々と切り、煮、焼き、皿を洗う。床を掃き卓を拭き、暖簾をかけ続ける昭和史であり、令和の時代も続いている。2021/03/20
Tadashi_N
27
昔ながらの良いお店。レパートリーを増やしたかった。2021/08/15
Humbaba
11
どのような状況であれ、人は食事なしに生きることはできない。現代は普通に暮らしていれば餓死など想像することもないが、それが当たり前であるという幸福な時代はあくまでも現代だからこそである。その時代に戻る必要はないが、そんな時代があったという記憶はなくしてはいけないだろう。2016/03/30
てくてく
6
アンチチェーン店ということで、チェーン展開しておらず、店主も広報よりも来客者の対応(つまりは味の工夫とその維持)に熱心がお店をとりあげている。もちろん森氏なので味のレポートというよりは店主と店の歴史の危機語りがメイン。東京が中心なので行ったことがないお店ばかりだったが、その名は聞いたことのあるお店は何軒かあって、行ってみたいと思った。「一番大変なのは食材と人材ですね。いい材料を仕入れること。人を育てること。これがなかなかうまくいきません。(後略)」(まい泉)など職人さんが取り上げられていて楽しかった。2014/12/15
Hiroki Nishizumi
5
広い意味でのグルメガイドとして読了。染太郎、土手の伊勢屋、リストランテ文流、などなど未踏の店に行きたい・・・2014/03/08