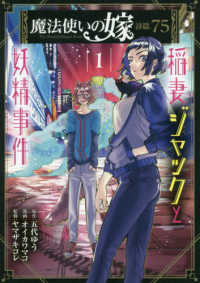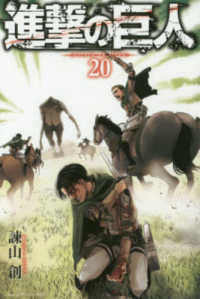出版社内容情報
歌舞伎、能、茶の湯、俳句、禅…日本の伝統芸能はなぜ海外で人気なのか。ポイントを厳選し解説。日本人としての自信と誇りが甦る本!
【著者紹介】
明治大学教授
内容説明
歌舞伎、能、茶の湯、俳句…海外で絶大な人気を誇る「ニッポンの伝統芸能」。しかし、当の日本人は「何が面白いのかわからない」という人がほとんど。そこで、「最低限これだけは知っておきたい」というポイントを厳選&明快解説。予備知識ゼロでも楽しく読める一冊。
目次
序章 なぜ今、「伝統芸能」なのか
第1章 人間関係を芸術化した「茶の湯」
第2章 役者の身体芸に酔う「歌舞伎」
第3章 夢幻の世界へと観る者を誘う「能」
第4章 「わざ・さび」は楽しい!「俳句」
第5章 日本人の「心の最大資産」である「禅」
著者等紹介
齋藤孝[サイトウタカシ]
1960年、静岡県生まれ。東京大学法学部卒業。同大学大学院教育学研究科博士課程を経て、明治大学文学部教授。専門は教育学、身体論、コミュニケーション論。著書に『声を出して読みたい日本語』(草思社文庫、毎日出版文化賞特別賞受賞)、『身体感覚を取り戻す』(NHKブックス、新潮学芸賞受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ともとも
31
禅、茶道、歌舞伎、能、俳句。 趣があって、奥深い、そして多くの気持ちや意味も 込められている。 日本の伝統芸能=日本人の歴史とアイデンティティ、を痛感しながらも それが人の子ことを育てていくこと、今に受け継がれている凄さ、 そして面白さ、素晴らしさがある。 日本の日本の伝統文化、芸能の魅力が詰まった1冊で良かったです。2016/02/29
メタボン
24
☆☆☆ 茶の湯、歌舞伎、能、俳句、禅について、日本の文化とからめてざっくりと説明した書。それぞれの味わい方についてもっと突っ込んでほしかったが、この5つのジャンルを1冊で紹介しようとすれば、このような形態にならざるをえないのだろう。興味を持てば巻末に紹介されている他の本をじっくり読むといいということか。2016/12/04
1.3manen
24
‘09年初出。ゴシ太本。自国の文化について語れない人はいくら英語が堪能でも深い信頼は得られません(7頁)。ご指摘のとおり。日本文化とは、日本人の感性や精神のあり方が開花した一形態(29頁)。話せない読書は価値が落ちてしまう(39頁)。読書会の必然性。本来娯楽、嗜好品のお茶が、死を背景にした厳粛な空間演出する中心へと昇華(54頁)。独座観念:客人を見送り茶室で独り考えに耽る(60頁)。歌舞伎とは宴(130頁)。幽玄:一種の香(143頁)。2015/02/24
ゆきこ
8
日本の伝統芸能の中から、茶の湯、歌舞伎、能、俳句、禅の5つを取り上げ、それぞれのおもしろさや楽しみ方を紹介しています。さらに、それら伝統芸能の根底に共通している日本人の精神性に言及されています。とても読みやすく、興味をひかれる内容です。個人的には特に俳句をやってみたい。様々な日本文化を通じて、教養を身につけたいと感じました。2015/09/10
てくてく
7
全くの初心者に面白さを強調するのであれば、こういう書き方になるのだろうかという印象。茶の湯、能、俳句をかじったことのある者としては、ところどころその説明に首をかしげてしまった。2016/11/01
-
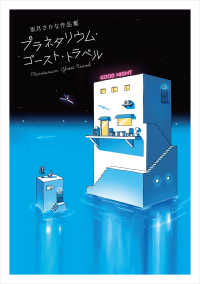
- 電子書籍
- 坂月さかな作品集 プラネタリウム・ゴー…