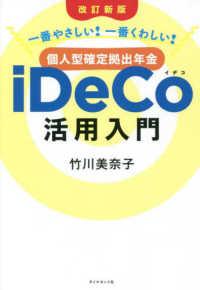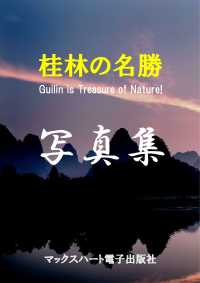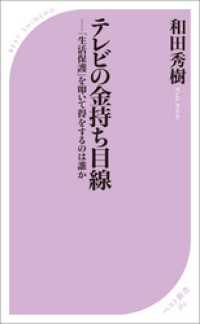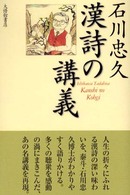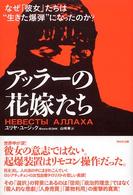内容説明
東京を東西に走る中央線のJR中野駅北側周辺は、かつて「囲町」と呼ばれていた。地名の由来は、その昔、この土地に「囲い」があったからである。では、なぜ「囲い」があったのか?その解答は本書を読んでいただくことにして、名所や地名には必ず、いわく・因縁があるものだ。本書では、江戸時代の名残をとどめる「江戸スポット」を紹介。その「スポット」たるウラ事情をお伝えする。
目次
第1章 江戸情緒あふれる名所へ(昔、本当に“三軒の茶屋”があった!?江戸の交通の要衝「三軒茶屋」―三軒茶屋;江戸の巨大遊郭「吉原」がもともと違う場所にあったワケ―千束 ほか)
第2章 歴史を彩った舞台をたずねる(「明暦の大火」の火元は本妙寺ではない!?まことしやかにささやかれる“火元引き受け説”―巣鴨;上野公園の不忍池が琵琶湖をマネてつくられたワケ―上野公園 ほか)
第3章 江戸っ子の生活風景を覗く(江戸の迷子専用掲示板だった「迷子しらせ石標」―日本橋;江戸時代には料金を徴収!?寛永寺にいまも残る「時の鐘」―上野公園 ほか)
第4章 江戸文化発祥の地を巡る(江戸っ子には門限があった!?夜十時には門が閉じられた高輪大木戸―高輪;『四谷怪談』で知られる「お岩稲荷」がなぜか四谷に二つもあるワケ―四谷 ほか)
第5章 武家社会の名残りをしのぶ(もともと、ふつうの町娘だった「護国寺」の創建者とは?―大塚;東京大学の「赤門」は江戸の婚姻政策のシンボルだった!?―本郷 ほか)