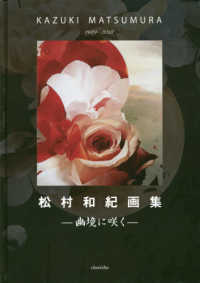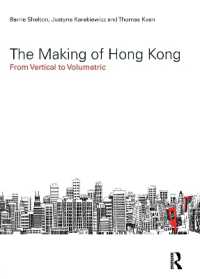内容説明
せっかくコーチングを学んだのに、現場へいくと「あれ?ケーススタディが役立たない!」―こんな人が多いのでは?本書では、多くの経営者・管理者を指導してきたカリスマ講師が、「実際に使うための」コーチングを平易に解説。「銀座NO.1ホステスに見るコーチング」など、ユニークな視点が満載で、類書につまずいた人でも「これなら使える!」こと請け合い。コーチング入門書の決定版、ついに文庫化。
目次
コーチングとは何か(注目される背景)
部下を伸ばすコーチング
聴くことと受け入れること
承認(褒めることと叱ること)
Iメッセージの力
聴くことと信じる能力
コミュニケーションから生まれるエネルギー
ペーシングはコミュニケーションの入り口
コーチングを妨げているもの
達成目標のビジュアライズ
質問をコーチングする
コーチングにおけるアドバイス
エネルギーロスを自覚する
コーチングのストラクチャー(構造)
相手を人生の主人公にする
著者等紹介
播摩早苗[ハリマサナエ]
(株)フレックスコミュニケーション代表。HBC北海道放送にアナウンサーとして勤務後独立。コミュニケーション心理学、自己表現、コーチングを学び、2001年に(株)フレックスコミュニケーション設立。現在、企業を対象とした人づくりのコンサルティング業務を軸とし、研修を設計・デザインしている。また、自らも講師として、管理職研修、営業職研修、プレゼンテーション研修のほか、士業、教員、医家などを対象としたオープンセミナー、女性のためのコミュニケーションセミナー、子育てに関するワークショップなどを中心に活動している。企業の経営者・管理職を対象に行なうエグゼクティブコーチングは、個人の業績向上とともに企業風土の変革にも寄与し、好評を得ている。さらに、ラジオ番組出演、経営者・管理職対象の講演などを通し、コーチングの普及活動も活発に行なっている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
読書ニスタ
西
たか
こうせいパパ
プランクマン