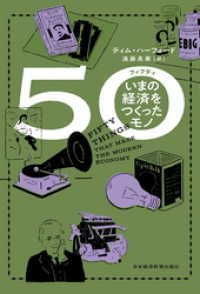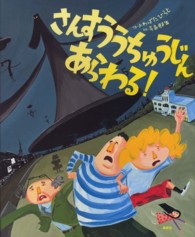出版社内容情報
「戦後日本」の成立経緯を検証する長編評論。
無条件降伏、マッカーサーの登場とその占領政策、そして東京裁判、新憲法の発布。「戦後」という時代を冷徹に見詰めた一級の歴史評論。
1945年8月15日、日本はポツダム宣言を受諾し、無条件降伏をした。ここに第二次世界大戦は終結。同月30日、連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーは、コーンパイプを燻らせつつ厚木に降り立った。以来2000日におよぶ日本占領が始まったのである。
▼その間、占領政策の下、昭和21年には日本国憲法が公布され、昭和23年には極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判の判決が下されるなど、激変する社会情勢のなか、「戦後の日本」がつくられていった。その立役者となったのは誰なのか。本書は、終戦から日本が自立復興の道を歩み出す、講和条約発効までを描いた、著者渾身の長編歴史評論である。
▼陸奥宗光、小村寿太郎、幣原喜重郎等、卓越した外交官にスポットを当てながら、近現代の日本の歩みと外交史を事実に即して克明かつ冷静にたどった、著者のライフワーク「外交官とその時代」シリーズ5部作の掉尾を飾る、堂々の完結編である。
●第1章 敗者日本の扱い
●第2章 東久邇宮内閣とマッカーサー
●第3章 自由とデモクラシーの復活
●第4章 勝者の心理と論理
●第5章 幣原の苦悩
●第6章 吉田茂の登場
●第7章 第一次吉田内閣
●第8章 東京裁判(その1)
●第9章 東京裁判(その2)
●第10章 占領軍の絶対権力
●第11章 潮の変り目
●第12章 再軍備のパラドックス
●最終章 公正な日本近代史を阻むもの
内容説明
1945年8月15日、日本はポツダム宣言を受諾し降伏した。同月30日、連合国軍最高司令官マッカーサーは厚木に降り立ち、2000日におよぶ占領が始まった。そして東京裁判、新憲法の公布。激変する社会情勢のなか日本は復興への道を歩み出したのだった。この「戦後日本」は誰がどのようにしてつくったのか。歴史の事実を克明にたどりつつ「戦後とは何か」を考える、著者渾身のシリーズ完結編。
目次
敗者日本の扱い―無条件降伏とは勝者による敗者の完全征服であった
東久邇宮内閣とマッカーサー―天皇制保全のため日本人はいかなる屈辱にも耐えた
自由とデモクラシーの復活―幣原は日本人の手による再建と改革に情熱を傾けた
勝者の心理と論理―占領政策は日本徹底改革論と対ソ戦略論に分かれた
幣原の苦悩―一月二十四日、幣原はマッカーサーと何を話したのか
吉田茂の登場―主義、思想とは無縁の外交官が首相になるまで
第一次吉田内閣―食糧問題と農地改革に尽力し新憲法を公布するまで
東京裁判(その一)―「極東国際軍事裁判の判決は史上最悪の偽善です」(ウイロビー)
東京裁判(その二)―判決の歴史観に対して正面から反論した二人の識見
占領軍の絶対権力―追放と言論統制が日本人の精神構造に深い傷を遺す
潮の変り目―敗戦直後「赤旗の海」だった日本が復興の道を歩むまで
再軍備のパラドックス―吉田茂はマッカーサーの方針を忠実に守りつづけた
公正な日本近代史を阻むもの―憲法第九条と東京裁判史観
著者等紹介
岡崎久彦[オカザキヒサヒコ]
1930年大連生まれ。東京大学法学部在学中に外交官試験に合格し外務省に入省。1955年ケンブリッジ大学経済学部学士及び修士。在米日本大使館、在大韓民国大使館などを経て、1984年初代情報調査局長に就任する。その後も駐サウジアラビア大使、駐イエメン大使を務め、1988年より駐タイ大使。1992年退官。現在は岡崎研究所所長。著書に『隣の国で考えたこと』(中央公論社、日本エッセイストクラブ賞)、『国家と情報』(文芸春秋、サントリー学芸賞)など多数
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
読書ニスタ
James Hayashi
James Hayashi
ceskepivo
日の光と暁の藍