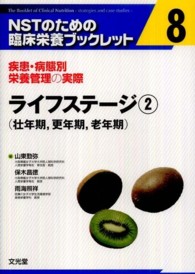出版社内容情報
最新のトピックスを中心に描き出す古代史。
近年明らかになったトピックスを中心に、邪馬台国論争や前方後円墳の謎にまつわる諸説をわかりやすく紹介。ロマンあふれる古代史。
旧石器発掘捏造事件、高松塚古墳壁画の解体――。近年、日本の考古学といえば深刻な話題ばかり。だが、古代史へのロマンは人々を魅了してやまない。今こそ、戦後六十年の研究の歩みを振り返り、その地道な成果の積み重ねを再検証すべきであろう。
▼吉野ケ里や三内丸山遺跡などの発見は大ブームを生み、最新科学は新たな史実を浮かび上がらせた。はたして、戦後の考古学は古代史の謎にどこまで迫れたのか。
▼各遺跡の最新情報から、邪馬台国や前方後円墳などにまつわる諸説までを、わかりやすく解説。
▼
[目次より]第1章 岩宿の発見から「捏造」の露見まで/第2章 モースの夢と縄文の花開く三内丸山/第3章 登呂遺跡と戦後考古学の復興/第4章 日本列島改造の波と保存運動/第5章 国民的永遠の謎/第6章 大和政権のモニュメント 前方後円墳/第7章 高松塚古墳は救えるのか/第8章 石の宮都・飛鳥の全貌/第9章 信長・秀吉の栄華にも考古学のメス/第10章 考古学の未来
●第1章 岩宿の発見から「捏造」の露見まで
●第2章 モースの夢と縄文の花開く三内丸山
●第3章 登呂遺跡と戦後考古学の復興
●第4章 日本列島改造の波と保存運動
●別章1 北海道における戦後考古学発見史
●第5章 国民的永遠の謎
●第6章 大和政権のモニュメント 前方後円墳
●第7章 高松塚古墳は救えるのか
●別章2 沖縄と南西諸島の先史文化探求
●第8章 石の宮都・飛鳥の全貌
●第9章 信長・秀吉の栄華にも考古学のメス
●第10章 考古学の未来
内容説明
旧石器発掘捏造事件、高松塚古墳壁画の解体―。近年、日本の考古学といえば深刻な話題ばかり。だが、古代史へのロマンは人々を魅了してやまない。今こそ、戦後六十年の研究の歩みを振り返り、その地道な成果の積み重ねを再検証すべきであろう。吉野ケ里や三内丸山遺跡などの発見は大ブームを生み、最新科学は新たな史実を浮かび上がらせた。はたして、戦後の考古学は古代史の謎にどこまで迫れたのか。各遺跡の最新情報から、邪馬台国や前方後円墳などにまつわる諸説までを、わかりやすく解説。
目次
岩宿の発見から「捏造」の露見まで
モースの夢と縄文の花開く三内丸山
登呂遺跡と戦後考古学の復興
日本列島改造の波と保存運動
北海道における戦後考古学発見史
国民的永遠の謎
大和政権のモニュメント前方後円墳
高松塚古墳は救えるのか
沖縄と南西諸島の先史文化探求
石の宮都・飛鳥の全貌
信長・秀吉の栄華にも考古学のメス
考古学の未来
著者等紹介
山岸良二[ヤマギシリョウジ]
1951年、東京都生まれ。慶應義塾大学大学院修士課程修了。日本考古学専攻。現在、東邦大学付属中高等学校教諭。日本考古学協会理事、習志野市文化財審議会会長などを務める。「方形周溝墓」を中心とする弥生時代墓制の研究や、「独鈷石」と呼ばれる縄文特殊石器の研究をメインとする論文が多い。その一方で、「わかりやすい考古学」を念頭に、一般向け啓蒙書の編著も数多い。また、最近は教育問題での発言も展開している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ツバメマン★こち亀読破中
寝落ち6段
おらひらお
takao
桑畑みの吉