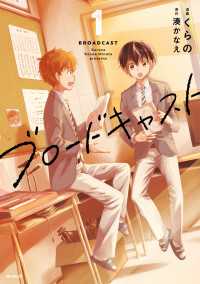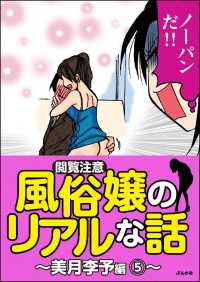出版社内容情報
この国を形づくるものを探訪する紀行エッセイ。
伊勢、熊野、瀬戸内などを訪ね歩き、海、山、平地の複合景観が、融合と調和の風土を生み出している日本文化の深層を探った紀行エッセイ。
日韓の複眼的視点を持つ著者が、日本列島の各地を旅して綴った紀行エッセイである。レトロの魅力に包まれる小樽、下北半島・恐山で感じた「あの世」、匠の伝統が生きる飛騨高山、ものづくり王国・三河、村上水軍が支配した瀬戸内海。さらに日本人の心を訪ねて富士山、伊勢神宮、熊野古道、高野山へ。都会を離れて見えてくる、豊饒で多彩な日本文化の諸相とは。
▼著者は日本独自の美しさをこう語る。「海原と平地集落と山塊が一挙に寄り集まって形づくられる風景、神仏が混淆した調和の文化、和風モダンを演出する空間……。私は日本に来てからずっと、これらの風景の美しさに魅せられ続けてきた」
▼全国各地を旅しながら、歴史、風土、人情にふれ、この国の神秘性に思いを馳せる。日本人には当たり前のものとして、とくに意識することはなかった風景が、著者の眼を通すことによって新鮮に見えてくるのだ。まさに美しい日本を再発見できる旅への招待である。
●第1章 懐かしい風景との出会い 日本人の心を癒す北の町(小樽・歴史編)――明治・大正ロマンの懐かしさが観光客を呼ぶ /レトロの魅力に包まれて歩く(小樽・町づくり編)――「また訪ねたい町」をつくる人々との出会い /高山・匠の伝統が生きる町(飛騨高山)――縄文以来の「文化の交差点」で独特な技術は育まれた /ものづくり王国・三河の精神(常滑・半田・岡崎)――「自然技術」の伝統はトヨタ生産方式に受け継がれた
●第2章 つわものたちの残像 海を支配した武士たち(瀬戸内海)――村上水軍が物語るもう一つの日本精神史 /源頼朝と伊豆の豪族たち(伊豆半島北部)――流離する貴種への憧れが生んだ「天下取り」への決起
●第3章 お山にこめられた信仰 なぜ日本人は富士に魅かれるか(山梨県富士吉田・静岡県富士宮など)――荒々しくも美しい霊山の頂に神仏の地上天国を見た /恐山で感じた「あの世」(下北半島・恐山)――この国特有の地蔵信仰に見た日本人の死生観
●第4章 この国を形づくるもの 海と山の複合景観と日本人の心(伊勢志摩)――日本独自の地勢が融合と調和の文化を生んだ /熊野信仰と日本人の自然観(紀州熊野)――神仏混淆に時代の先端に位置する精神を見た /高野山はなぜ日本人の聖地か(和歌山県高野山)――仏教と民間信仰が共存するこの国の「普遍意識」
内容説明
日韓の複眼的視点をもつ著者が、各地を旅して綴った紀行エッセイ。レトロの魅力に包まれる小樽、下北半島・恐山で感じた「あの世」、匠の伝統が生きる飛騨高山、村上水軍が支配した瀬戸内海。さらに日本人の心を訪ねて富士、伊勢神宮、熊野古道、高野山へ。都会を離れて見えてくる、豊饒で多彩な日本文化の諸相とは。新鮮な感動が伝わってくるニッポン再発見の旅。
目次
第1章 懐かしい風景との出会い(日本人の心を癒す北の町(小樽・歴史編)―明治・大正ロマンの懐かしさが観光客を呼ぶ
レトロの魅力に包まれて歩く(小樽・町づくり編)―「また訪ねたい町」をつくる人々との出会い ほか)
第2章 つわものたちの残像(海を支配した武士たち(瀬戸内海)―村上水軍が物語るもう一つの日本精神史
源頼朝と伊豆の豪族たち(伊豆半島北部)―流離する貴種への憧れが生んだ「天下取り」への決起)
第3章 お山にこめられた信仰(なぜ日本人は富士に魅かれるか(山梨県富士吉田・静岡県富士宮など)―荒々しくも美しい霊山の頂に神仏の地上天国を見た
恐山で感じた「あの世」(下北半島・恐山)―この国特有の地蔵信仰に見た日本人の死生観)
第4章 この国を形づくるもの(海と山の複合景観と日本人の心(伊勢志摩)―日本独自の地勢が融合と調和の文化を生んだ
熊野信仰と日本人の自然観(紀州熊野)―神仏混淆に時代の先端に位置する精神を見た ほか)
著者等紹介
呉善花[オソンファ]
1956年、韓国・済州島生まれ。韓国女子軍隊経験をもつ。1983年に来日し、大東文化大学(英語学専攻)の留学生となる。その後、東京外国語大学大学院修士課程(北米地域研究)を修了。現在、評論家、拓殖大学国際開発学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。