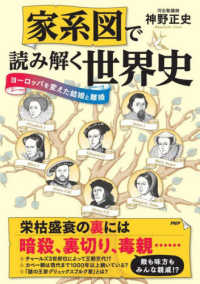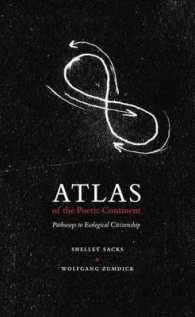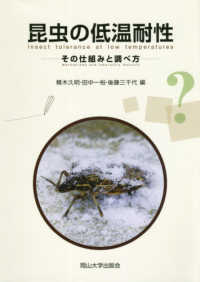出版社内容情報
宗教社会学の立場から、宗教を解き明かす!
宗教は不可思議なものではない。人間の営みであり、そこには一定の法則性がある。「宗教とは何か」を宗教社会学の立場から、解き明かす。
日本では、「あなたの宗教は?」という問いに、「無宗教です」と答える人が数多い。しかし、たいていの日本人は「初詣には神社に行き、結婚式はキリスト教、葬式は仏教で」と、人生の節目にさまざまな宗教と深く関わっている。それだけではない、実は何気ない日常的な行為の中にも宗教的な意味あいを持ったものがたくさんある。いったい私たちにとって宗教とは何なのか? 本書では、宗教を人と人とのコミュニケーションから生まれた社会現象としてとらえ、宗教社会学の立場から「宗教のしくみ」を解説している。個別の宗派や教団の説明ではなく、宗教の定義・分類に始まり、教えや儀礼の話、死生観、データにみる日本人の宗教観など、きわめて客観的に宗教を分析する。そこにあるのは偏見や先入観を排して、冷静に宗教を見つめる目である。グローバル化が進み、さまざまな価値観や宗教観に触れる機会が多くなった現在、ぜひとも一読しておきたい一冊といえる。
●第1章 新しい宗教の見方・考え方
●第2章 宗教を解剖する
●第3章 宗教はどのように発展してきたのか
●第4章 日本人にとって宗教って何だろう
内容説明
宗教社会学とは、ひとことでいうと、「人間の営みとしての宗教を、客観的な立場から研究する学問」ということになります。そして、そこから導かれる大前提は三つあります。第一に、宗教は人間の営みであるから、社会・地域・時代とともに変化すること。第二に、その変化の結果、同じ宗教にも多様性が出てくること。そして第三に、人間の思惑や願望によって、宗教は人間の意図した通りには必ずしも展開しないこと、などです。このような見方・考え方から宗教を見たとき、どのようなことがわかるのか、というのが本書の意図です。
目次
第1章 新しい宗教の見方・考え方(宗教は社会現象である;「宗教」を定義することはできるの? ほか)
第2章 宗教を解剖する(聖典は一日にしてならず;宗教には免疫反応がある ほか)
第3章 宗教はどのように発展してきたのか(人はカリスマを求める;教団はどのようにして発生し、成長するのか? ほか)
第4章 日本人にとって宗教って何だろう(本当に日本人は無宗教なの?;日本には宗教の信者はどのくらいいるの? ほか)
著者等紹介
岩井洋[イワイヒロシ]
1962年奈良県生まれ。上智大学大学院博士後期課程満期退学。現在、関西国際大学人間学部助教授。宗教社会学、文化社会学を専攻
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 6股彼氏 至上最高の復讐を【タテヨミ】…