出版社内容情報
難解なケインズの「一般理論」をやさしく解説。
経済学の基本中の基本といわれるケインズの『雇用、利子および貨幣の一般理論』(いわゆる一般理論)を図解と具体例でやさしく解説。
経済学を学ぶ人が必ず目を通さなければならない必読書といえば、ケインズの『雇用・利子および貨幣の一般理論』であろう。1936年に発表されたこの本は、まさに近代経済学の礎ともなる本であり、彼の理論は「ケインズ革命」とまで称された。その哲学は、いまでもケインジアンといわれる人々によって脈々と受け継がれている。
▼本書は、とかく難解といわれるケインズの『一般理論』を、大学生でも理解できるようやさしく解説している。特にそのエッセンスである乗数理論、有効需要、所得速度、消費性向、流動性選好などの概念を、落語のたとえ話を用いたりして工夫している。
▼本書のもう一つの大きな特徴は、ケインズ理論の誤解を解くことにある。いまや各国で行なわれている金利操作だが、なぜ史上空前の低金利でも日本の景気は浮揚しないのか。また公共投資もそれほど効果がないのか。実は『一般理論』をよく読めばちゃんと答えが書いてあるのである。
●第1章 今、なぜケインズか
●第2章 ケインズの『一般理論』を読む
●第3章 ケインズは本当に死んだのか
●第4章 ケインズ理論は生きている
内容説明
経済学の名著『雇用・利子および貨幣の一般理論』のエッセンスをわかりやすく解説。そこから見えてきたケインズの真意とは。
目次
第1章 今、なぜケインズか(大不況が『一般理論』を生んだ―ケインズ理論の歴史的背景;古典派・新古典派からの脱却―ケインズ革命の本質を探る ほか)
第2章 ケインズの『一般理論』を読む(「投資が先か、消費が先か」の議論に終止符を打つ―消費こそ経済の原動力;消費性向を動かす要因―消費を決定する要因 ほか)
第3章 ケインズは本当に死んだのか(ケインズ経済学の悲劇の始まり―ケインズ理論の誤解と悲劇;悪用されたケインズのメカニズム―ケインズ以後の金融機構)
第4章 ケインズ理論は生きている(国債発行に依存することの是非―後世に借財を残す;何をなすべきなのか―完全雇用と所得の再配分 ほか)
著者等紹介
入江雄吉[イリエユウキチ]
昭和2年、東京都生まれ。昭和26年、慶応義塾大学経済学部卒業。昭和29年、同大学大学院経済学研究科博士課程入学。理論経済学専攻。昭和32年、同大学博士課程修了(理論経済学の研究を継続しつつ、某金融機関において国際投融資の実務に従事する)。昭和59年、経済研究所設立。元嘉悦女子短期大学教授。国際エコノメトリック学会会員、日本経済学会会員、日本学術会議登録メンバー
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
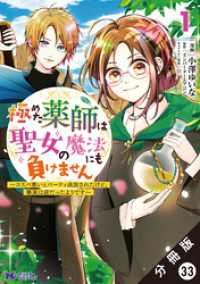
- 電子書籍
- 極めた薬師は聖女の魔法にも負けません …



