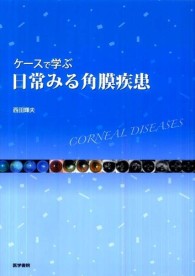出版社内容情報
古代人はより神に近い所で宇宙を見ていた!
ストーンヘンジからマチュ・ピチュまで、世界各地に遺された古代遺跡と太陽信仰の関係性を探る。ロマンあふれる天文考古学の入門書。
イギリスのウェセックス地方に遺るストーンヘンジと呼ばれる環状列石、アイルランドのニューグレンジにある洞窟、エジプトのカルナック神殿、古代アステカ王国のテノチティトランにある太陽の神殿……。これら世界各地に点在する遺跡は、すべて古代人の天文台だった。当時の人々にとって、闇は恐怖であった。また、農耕へ移行した彼らにとって、太陽の天空上の運行を知ることは、食糧を確保する上でも不可欠なことであった。そのため彼らは、太陽を神と崇めたのである。本書では、古代文明を築き、発展させた人々が、どのような描像を天空を翔ける星々や太陽、月、あるいは惑星たちについて持っていたかについて思いをはせる。古代人の心を知ることは、現代に生きる私たちが、その知的伝統をどのように継承してきたか、またそれに基づいてどう未来を展望すべきかを考えるきっかけになるだろう。古代への憧憬と天文ロマンを融合させた学問「天文考古学」の入門書。
●太陽への憧れ
●太陽への畏敬
●太陽が生む恐怖
●太陽を見る
●太陽の彼方へ
●太陽と月
●太陽と星々の世界
内容説明
本書では、太陽と、文字で記録を残す以前の考古学的な古代世界との関わりについて、世界各地に残る遺跡を訪ねながら、最近誕生した新しい学問である考古天文学について案内することを試みる。
目次
太陽への憧れ―恵みをもたらすもの
太陽への畏敬―太陽神の誕生
太陽が生む恐怖―血の犠牲
太陽を見る―四季を測る
太陽の彼方へ―天への階段
太陽と月―天空を翔けるもの
太陽と星々の世界―夜と昼はなぜできる
著者等紹介
桜井邦朋[サクライクニトモ]
昭和8年埼玉県生まれ。京都大学理学部卒。高エネルギー宇宙物地学の世界的な権威。京大助教授を経て、昭和43年招かれて、NASA主任研究員になる。昭和50年、メリーランド大学教授。帰国後昭和52年より神奈川大学工学部教授。ユトレヒト大学、インド・ターター基礎化学研究所、中国科学院などの客員教授も務める。理学博士
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。