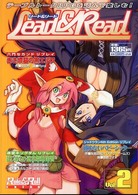出版社内容情報
21世紀の日本はどう創られるべきか。90年代の日米両国を比較しながら、日本における「知価社会」実現のための方策を両論客が提言する。
90年代は、アメリカにとって「実りの10年間」であったといわれる。この10年間にアメリカは、長らく続いた冷戦を終結させ、そのあとに「一人勝ち」の体制をつくることに成功したからだ。
▼対する日本の90年代は、「失われた10年」といわれるほど、実りも進歩も乏しいものであった。バブル景気崩壊の後遺症だけではない。外交的成果も乏しかったし、教育も荒廃した。モノづくりも技術に陰りが見え始め、安全神話も崩れつつある。
▼しかし何よりも深刻なのは、日本国民の多くが、自国の将来に対して、明るい展望と自信を失っていることではないだろうか。同じく自由主義経済を標榜し、共に西側陣営にあって冷戦に勝利したはずの日米両国に、なぜこれほどの違いが生じてしまったのか――。
▼近年の日米両国の歩みを見定めてきた両著者は、その原因を「知価革命の時期と速度の差」だとし、この国に楽しみと誇りをもたらすための方策、そして「進むべき道」を提示する。
●序章 日米それぞれの視点で
●第1章 日米逆転の十年間
●第2章 フロンティア・スピリットと集団主義
●第3章 大学と青年
●第4章 地域構造と情報発信
●第5章 都市の暮し・法治の姿
●第6章 日米財政の経験と見直し
●第7章 日本の消費を拡大するには
●第8章 新世紀を考える二つの要点――石油と知価
内容説明
「実りの十年」と「失われた十年」どこで何が違ったのか?!日米この10年の歩みを見定め、21世紀の針路を問う。前経済企画庁長官とエール大学教授、碩学二人の対話。
目次
序章 日米それぞれの視点で
第1章 日米逆転の十年間
第2章 フロンティア・スピリットと集団主義
第3章 大学と青年
第4章 地域構造と情報発信
第5章 都市の暮し・法治の姿
第6章 日米財政の経験と見直し
第7章 日本の消費を拡大するには
第8章 新世紀を考える二つの要点―石油と知価
著者等紹介
堺屋太一[サカイヤタイチ]
1935年、大阪生れ。東京大学経済学部卒業とともに通産省に入る。日本万国博覧会を企画、開催にこぎつける。1978年、通産省を退官、執筆・講演活動に入る。税制調査会委員、国会等移転審議会委員、中央省庁等改革推進本部顧問を歴任。1985年より1998年、(財)アジアクラブ理事長、1998年7月より2000年12月、国務大臣・経済企画庁長官を務める。現在、内閣特別顧問。著書に、『豊臣秀吉(上・下)』『鬼と人と(上・下)』『知価革命』『組織の盛衰』『あるべき明日』『未来への助走』(PHP研究所)、『日本を創った12人(前編・後編)』(PHP新書)、『油断!』(日本経済新聞社)、『団塊の世代』『日本とは何か』(講談社)、『秀吉(上・中・下)』(NHK出版)、『巨いなる企て』『欣求楽市』(毎日新聞社)、『明日を想う』(朝日新聞社)など多数
浜田宏一[ハマダコウイチ]
1936年、東京生れ。東京大学法学部、同大学経済学部卒業。エール大学Ph.d.(経済学)。東京大学経済学部教授を経て、エール大学経済学部教授。1997年、IMF構造調整融資プログラム外部評価委員。1999年、経済企画庁経済研究所顧問。2001年1月より内閣府経済社会総合研究所所長。著書に、『国際金融の政治経済学』(創文社)、『損害賠償の経済分析』(東京大学出版会)、『金融(館龍一郎氏との共著)』『国際金融』(岩波書店)、『金融政策と銀行行動(岩田一政氏との共著)』(東洋経済新報社)、『エール大学の書斎から』(NTT出版)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- わけありシングルママの再会愛【タテヨミ…