出版社内容情報
近代化の期待を一身に担って留学した英文学者・漱石の「不愉快」なロンドン体験から、明治日本が抱えていたジレンマの本質に迫る。 1900年9月、第五高等教育学校教授であった夏目漱石は、2年間のイギリス留学へと旅立った。しかしこの留学生活は、後に「ロンドンに住み暮らしたる2年はもっとも不愉快の2年なり」と語られることになる。栄ある第1回官費留学生・漱石の「不愉快」の原因とは一体何だったのか。本書では、漱石自らが失敗作と認める『文学論』と、優れた18世紀英文学論である『文学評論』という、2冊の著作が執筆された背景を探りながら、これらの問いを解き明かしていく。文明開化のシンボルたる「英語」と、実学の対極に位置する「文学」の狭間で揺れる「英文学」という学問の意味。文明開化の担い手としての役割を期待されながら、イギリスで、近代化が人間の精神を衰弱させていく過程を目の当たりにするというジレンマ。漱石のみならず、明治の知識人が不可避に抱え込まざるを得なかった苦悩、そして近代化の残酷な宿命を浮き彫りにした、出色の漱石論である。
内容説明
近代化の期待を一身に担い、初の官費留学生としてロンドンに旅立った夏目漱石。しかし、その留学の二年間は、後に「倫敦に住み暮らしたる二年はもつとも不愉快の二年なり」と語られる。漱石にとって英文学を学ぶこととは何であったのか。彼がイギリスで目の当たりにした「開化」の酷薄な宿命とは何だったのか。英文学者としての二つの著作『文学論』と『文学評論』が書かれた背景を探りながら、漱石の「不愉快」の正体、ならびに、明治日本が不可避的に背負ったディレンマの本質に迫る力作評論。
目次
第1章 新しい世紀の始まり
第2章 イギリス留学
第3章 不愉快な気分
第4章 現代日本の開化
第5章 『文学論』の悲惨
第6章 『文学評論』と開化
第7章 開化の行く末
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
TakaUP48
猫丸
Ted
くにお
-
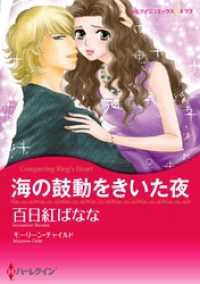
- 電子書籍
- 海の鼓動をきいた夜〈【スピンオフ】キン…
-
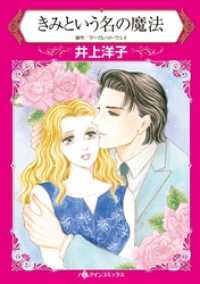
- 電子書籍
- きみという名の魔法【2分冊】 2巻 ハ…
-
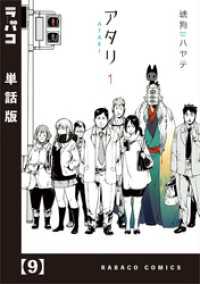
- 電子書籍
- アタリ【単話版】 9 ラバココミックス
-
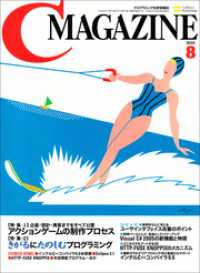
- 電子書籍
- 月刊C MAGAZINE 2005年8…





