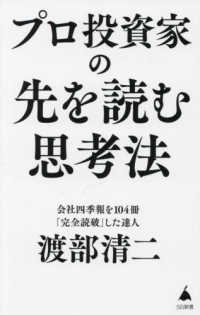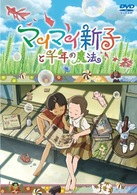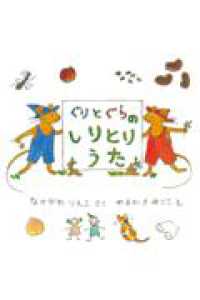出版社内容情報
子どもの優しさと意欲の育み方をアドバイス。
自分本位で無気力な子どもを、思いやりがあり意欲的な子どもに育てたい。著者の体験を交えて情緒豊かな子どもの育て方をアドバイス。
子どもが「よい子」に育つことを願うあまり、口ごたえを理由も聞かずに叱ってしまう。そんな親が意外と多いもの。しかし、本当の「よい子」とは親の言うことを何でも聞く子どものことではありません。むしろそういう子どもは思春期に問題児となる恐れさえあります。逆に、幼児期に親をてこずらせた子どものほうが、長い目で見ると健全に成長しています。
▼本書は、「よい子」に必要な4つの要素を中心に、著者の長年の教育体験から得た”子育てのコツ”をまとめたもの。
▼それは(1)思いやりの心、(2)自分で考え行動する自発性、(3)集団の秩序を守る社会性、(4)知識だと言います。この4つをバランスよく身につけた子どもこそ、まさに「よい子」であり、そのような子を育てるには、親が思いやりをもち、子どもの反抗は自発性の発達だと理解し、秩序を守る判断力を身につけるように導くことが大切だと著者は言うのです。
▼子育てに悩む母親必読の一冊。
●第1章 子どもの「情緒」を豊かにする
●第2章 子どもの「意欲」を尊重する
●第3章 「適応能力」と「知的能力」をどう育てるか
●第4章 「しつけ」は必要ない――「ゆとり」ある子育ての実践を
内容説明
子供が「すなお」で「よい子」に育つことを望まない親はいないでしょう。しかし「よい子」とは、親の言いつけを何でもハイ、ハイと聞き入れる子供のことではありません。人を思いやる気持ちと積極性、友達と仲良くできる社会性、そして知識の4つをバランスよく身につけた子供こそ、まさによい子なのです。子供の可能性を最大限に伸ばす子育てバイブル。
目次
第1章 子どもの「情緒」を豊かにする(思いやりの心は親子関係の中ではぐくもう;「人見知り」はお母さんを信頼している証拠 ほか)
第2章 子どもの「意欲」を尊重する(いきいきと、充実した人生を求めて;「反抗期」があるから育つ自発性 ほか)
第3章 「適応能力」と「知的能力」をどう育てるか(適応能力とは何だろうか;がまんの心を教えよう ほか)
第4章 「しつけ」は必要ない―「ゆとり」ある子育ての実践を(なぜ子どもを叱ってしまうのか?;「しつけ無用論」―子どものお手本になろう ほか)
著者等紹介
平井信義[ヒライノブヨシ]
1919(大正8)年3月、東京生まれ。東京大学文学部、東北大学医学部卒業。母子愛育会愛育研究所所員を経てお茶の水女子大学教授、1970’(昭和45)年より大妻女子大学教授、1990(平成2)年より大妻女子大学名誉教授、児童学研究会会長。医学博士
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。