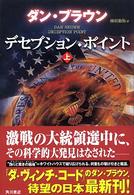出版社内容情報
共通語としての標準語誕生の経緯を解説する。
標準語はいつ、どのようにして成立したのか。歴史の流れとことばの変遷に注目しつつ、共通語としての標準語誕生の経緯を明らかにする。
現在、日本全国で使われている、いわゆる“標準語”に相当する「共通ことば」は、いつ、どのようにして成立したのか。歴史の流れとことばの変遷に注目しつつ、その成立の経緯を明らかにしようというのが本書の試みだ。
▼標準語というニュアンスには、戦前までの国語教育が方言を悪としたことから、否定的先入観を抱く人もいよう。しかし、その土地独自の標準語をもつべきと主張する著者の視点は、あくまでも言語を使う庶民の意識に向けられており、そうした先入観は払拭されるに違いない。
▼日本における標準語に相当していたのは、中世末期までは京や大坂の上流階級が使う上方語だったという。だが江戸開幕以降、武士や町人の往来により、次第に江戸語がその地位を得たそうだ。標準語教育が始まる明治以前、既に庶民には江戸語が標準語という認識があったという指摘には驚かされる。
▼他にも各地の方言を調べ、標準語のルーツを探るなど、興味深い研究事例が満載である。
●第1章 宣教師たちの日本語感覚
●第2章 町人たちの日本語講義
●第3章 「標準語」の登場
●第4章 ことばと地理
●第5章 ことばと歴史
●第6章 ことばと社会