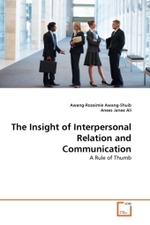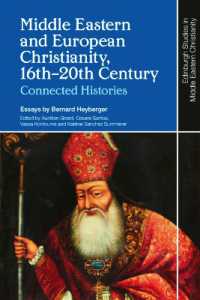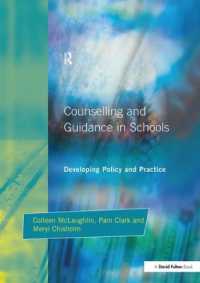内容説明
本書において、著者は、サンボリスムを、孤立した現象としてではなく、中世晩期―マニエリスム―ロマン派―サンボリスム―現代芸術という、アリアドネの糸の一環として総体的関連のうちにながめ、逆にサンボリスムを手掛りにして大きなコンテキストをたえず確認しようと試みる。著者ハンス・H・ホーフシュテッターは、さきに同じ訳者によって訳出された「迷宮としての世界」の硯学G・R・ホッケの弟子であり、本書はこのマニエリスム研究と照応し相補う位置におかれる労作である。
目次
1 19世紀のサンボリスム的相貌
2 19世紀芸術におけるサンボリスム
3 サンボリスムの様式フォルム
4 サンボリスムの表象世界
5 付録―文献資料集
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ソングライン
15
自然的な実在をただ描くのではなく、内に感じたものを象徴として描く象徴主義(サンボリズム)絵画はいつの時代にも存在しますが、19世紀とういう革命後のブルジョワの台頭、彼らが基準とした古典的なもの、自然主義的なものから離反した象徴主義の芸術家たちの作品を本書では解説していきます。女と死、地上の快楽と彼岸の恐怖との同一性の予感などを象徴的に描く画家たち、ベックリン、ロセッティ、ルドン、モロー、シャヴァンヌなどが登場します。2021/08/11
mstr_kk
6
象徴主義について調べるために読みました。僕の関心は文学なのですが、この本は美術が中心。それでも、序盤の歴史的な解説・美学的な意味づけの部分はたいへん勉強になりました。ちなみに、この著者は「象徴」を用いる芸術を広く「象徴主義的芸術」と呼んでおり、19世紀末のサンボリズム以外のものも論じています。2016/05/28
Yoko Kakutani 角谷洋子/K
2
ホッケの弟子、ホーフシュテッターの大著。難しくてよく分からなかった。サンボリズムを中世後期ーマニエリスムーロマン派ーサンボリズムー現代芸術という流れから読みといているらしい。私の好きなベックリンやシュトゥックについて踏み込んだ分析があるのは良かった。2020/02/14
生きることが苦手なフレンズ
0
最近、近所にできた古本屋で買いました。象徴主義、世紀末美術は好きなので、楽しく読めました。特に、「ピエロ」や「楽園」について述べた表象世界の研究は言語化できなかったものを形にしてくれた満足感があります。「はじめに」で書かれたとおり、「分析がまったく不可能であるようなひとつの複合体」を分析した「虚構」かもしれませんが、読者として、直観的綜合をなす道標になるような気がします。2013/05/12